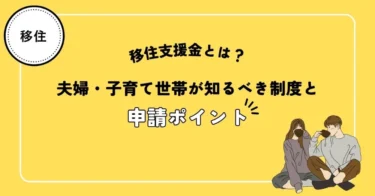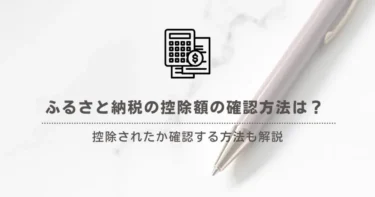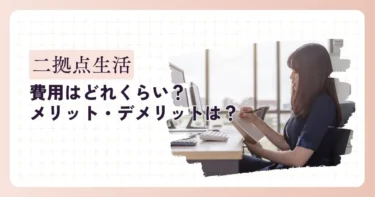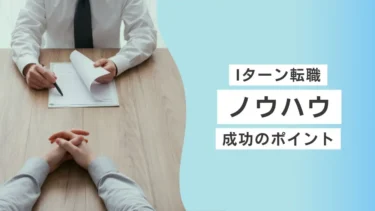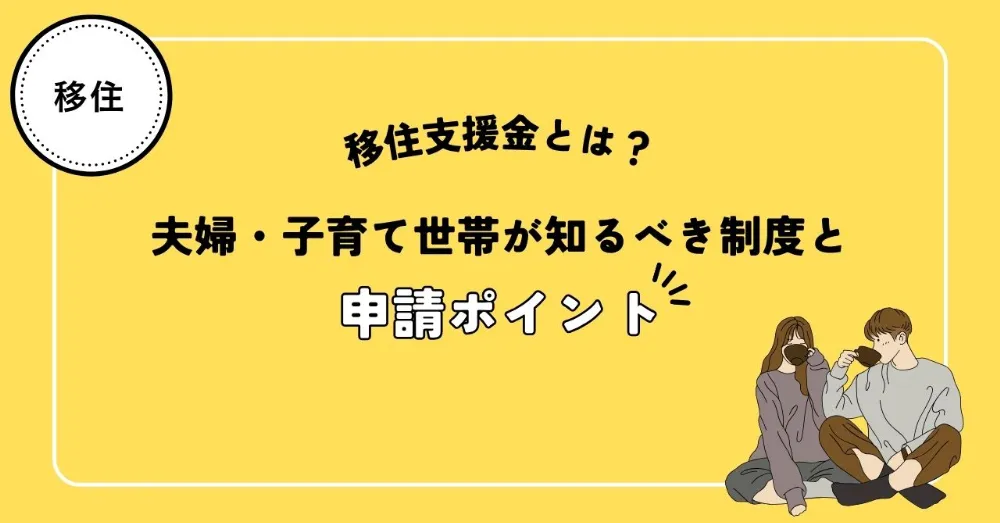
「子どもが小学校に上がる前に自然豊かな街へ移りたいけれど、引っ越し費用や仕事探しが不安」「夫婦ふたりだけの所得で新天地の生活を維持できるか心配」
そんな悩みを抱える家族を後押しするのが国と自治体が連携する「移住支援金」です。
夫婦世帯なら最大100万円、18歳未満の子ども1人につき最大100万円が加算される仕組みがあり、住宅取得や転職費用の負担をぐっと抑えられます。
この記事では、制度の内容から申請ステップ、支援が手厚い自治体の選び方、移住を成功させるポイントまでを総合的に紹介。子育て世帯でも失敗しない移住計画を具体的にイメージできる内容なので、地方移住を検討中のご夫婦はぜひ参考にしてください。
移住支援金の制度と対象
移住支援金は東京23区に在住・通勤する人が東京圏外へ移り、対象求人で働くか地域課題解決型の起業を行う場合に交付される制度です。
世帯への基本上限100万円に加え、子ども1人につき最大100万円、起業なら最大200万円を追加できるため、子育て世帯ほど恩恵が大きいのが特徴です。
夫婦・子育て世帯が受ける要件
主な要件は「連続5年以上23区在住または通勤」「移住先で対象求人に就業または起業」「移住後5年間定住」の3つです。夫婦で申請する場合、いずれかが産休・育休中でも雇用契約が継続していれば就業要件を満たすケースがあります。
移住先自治体が事業実施団体かどうか、対象求人に該当するかを必ず確認しましょう。
最大支給額と加算の仕組み
支給額は①世帯か単身か②子ども人数③起業加算の組み合わせで算出されます。
例えば、夫婦と子ども2人で起業を選択すると、基本100万円+子ども加算200万円+起業加算200万円で合計500万円が上限です。年度によって金額が見直されるため、最新版の交付要領を確認してから申請準備を進めてください。
夫婦・子育て世帯が得るメリット

都市部より低い住宅費と豊かな子育て環境を同時に手に入れられる点が最大のメリットです。
以下のポイントを押さえると移住支援金を活用した生活設計がイメージしやすくなります。
- 住居費と生活コストの軽減
- 安心できる子育て環境づくり
- ライフスタイルと時間の最適化
- 地方でのキャリア形成支援
- 地域コミュニティからの支援
それぞれのメリットが家計や暮らしにどう影響するのか解説していきます。
住居費と生活コストの軽減
地方都市や中山間地域の家賃相場は都心の半分以下となる例が多く、持ち家を取得しても毎月の返済負担は現状の家賃と同水準に収まります。水道光熱費も寒冷地手当や再エネ補助で実質コストが下がる自治体が増加しています。
移住支援金を頭金や敷金礼金に充当すれば引っ越し初期費用をほぼゼロに抑えられ、浮いた資金を教育費や余暇費に回すことで家計の安定と暮らしの充実を同時に実現できます。
さらに空き家バンク・リフォーム補助を組み合わせれば月々の支払いが賃貸並みで広い戸建てを手に入れ、庭先で家庭菜園やBBQを楽しむ生活も夢ではありません。
都市部では難しい車二台持ちも固定費が抑えられるため実現しやすく、買い物や送迎の利便性が大きく向上します。
安心できる子育て環境づくり
地方では待機児童ゼロを達成する自治体が多数あり、保育所や学童の入所がスムーズです。医療費助成を高校卒業まで全額無料とする地域や紙おむつ無償配布、子育て世帯向け家賃補助など独自施策が充実しています。
自然体験プログラムやICT教育を取り入れる公立校も増え、放課後には英語やプログラミングの教室が町内で完結するケースも。
経済負担を抑えつつ多様な学びを身近に選択できる点は進学や将来の職業選択の幅を広げ、親子双方に安心をもたらします。さらに広い公園や河川敷が身近にあることで、子どもがのびのび遊び健全な体力を育める環境が整います。
ライフスタイルと時間の最適化
平均通勤時間が片道1時間短縮されるだけで年間約240時間の自由時間が生まれ、家族で過ごす夕食や週末レジャーが格段に増えます。車社会が主流の地域では買い物や保育園送迎を効率良くこなせるため、家事や育児の分担がしやすく夫婦のストレスも軽減します。
澄んだ空気と広い公園、星空観察や川遊びなど自然に触れる機会が豊富で、子どもの感性も伸びやすい環境です. 休日に庭でBBQや家庭菜園を楽しみ、地域イベントで伝統文化を学ぶなど都会では得難い体験が日常化します。通勤や家事に充てていた時間を自己学習や副業に回すことでスキルアップも進み、将来設計の自由度が高まります。
地方でのキャリア形成支援
地方創生が進む現在、ITエンジニアやデジタルマーケターなど都市部で培ったスキルを求める求人が増えています。移住支援金対象求人なら企業にも補助が入るため採用意欲が高く、交渉次第でテレワーク併用やフレックスタイムなど柔軟な働き方を選択可能です。
副業解禁の流れも追い風となり、地域観光ライターやオンライン講師、ECサイト運営など複収入の道が開けます。地方銀行や商工会議所が起業セミナーを無料開催する地域もあり、少額でスモールビジネスを立ち上げるチャンスが豊富です。
地域企業と都市部企業のハイブリッド就業を実践する移住者も増え、多様な働き方を試せる土壌が整っています。
地域コミュニティからの支援
移住者向け交流会や地域食堂、子育てサロンを自治体が定期開催しており、同世代の家族や先輩移住者とすぐに交流できます。集落支援員が行政手続きを伴走し、農園体験や祭りの準備を通じて住民との距離が縮まる仕組みも整備されています。
顔の見える関係が築けることで子どもの見守りネットワークが自然と広がり、病児保育や送迎を助け合う環境が生まれやすいのが特徴です。
互助の文化が根付く地域では災害時の協力体制も強固で、家族の心理的安全性と暮らしの安心感が大幅に高まります。こうしたつながりは子どもの社会性を育むだけでなく、大人にとっても新しい趣味や友人を得るきっかけとなり、定住意欲を高める要因になります。
移住支援金申請のステップ

申請手続きは段取りを押さえれば難しくありません。
次の5ステップを順に進めることで、書類不備や手続き漏れを防ぎ、支給までの期間を短縮できます。
- STEP1 対象求人を探す
- STEP2 移住前の事前相談
- STEP3 引っ越しと就労決定
- STEP4 書類提出と面談
- STEP5 入金確認と定住フォロー
各ステップで押さえるべきポイントと注意事項を詳しく解説していきます。
STEP1 対象求人を探す
最初に「移住支援金対象求人」に登録された企業をハローワーク求人検索や各県のUIJターンポータルで調べます。検索時は〈移住支援金〉のタグ有無、リモート可否、勤務時間帯、家族手当など生活に直結する条件を細かく確認しましょう。
応募前に企業へ直接問い合わせ、制度を利用した前例の有無や定着率を聞き取ると安心です。転職エージェントを併用すれば非公開求人を紹介してもらえる場合もあり、選択肢が広がります。
求人票の控えをPDF保存しておくと、後の申請で「求人ID」を記入する際に役立つので忘れず保管してください。
STEP2 移住前の事前相談
対象求人の応募と並行して、移住予定自治体の移住コーディネーターへ早めに相談します。支援金を実施していない自治体もあるため、制度の有無と今年度予算の残額を確認することが重要です。空き家バンクの物件在庫、保育園の空き状況、子育て支援サービスの利用要件もこの段階で把握しておくと、後の書類準備がスムーズに進みます。
オンライン相談の録画や担当者名をメモしておくと、書類作成時のエビデンスとして活用でき、担当交代時も話が通りやすくなります。
STEP3 引っ越しと就労決定
内定が確定したら住民票を移し、実際に転居します。就業開始は移住後3ヶ月以内が原則のため、引っ越し日は就業開始の1〜1.5ヶ月前が目安です。引っ越し費用や敷金礼金は支援金の対象外ですが、自治体独自の転入補助がある場合は別途申請できます。
賃貸契約書や就業契約書、転入届の控えなどは支給申請の必須資料となるので原本とコピーを用意し、データ化してクラウドにも保存しておくと紛失リスクを避けられます。子どもの転校手続きや保育園入園申込は、自治体によって締切日が異なるため余裕を持って進めることが肝要です。
STEP4 書類提出と面談
転居後、指定期間内(おおむね3ヶ月以内)に申請書一式を自治体へ提出します。必要書類は〈移住支援金交付申請書〉〈誓約書〉〈住民票の写し〉〈就労証明書〉〈賃貸または売買契約書〉などで、起業の場合は〈事業計画書〉が追加となります。
面談では移住理由や今後5年間の定住計画を口頭で説明するため、家族のライフプランを夫婦で共有し、質問想定と回答メモを用意しておきましょう。
書類に不備があると再提出で支給時期が遅れるため、提出前にチェックリストで抜け漏れを確認し、コピーを取って控えを保管することが大切です。
STEP5 入金確認と定住フォロー
書類審査が完了すると、指定口座へ支援金が振り込まれます。自治体によっては入金まで1〜2ヶ月かかるため、資金繰りを考慮して一時的に生活費を余裕を持って確保しておくと安心です。入金後から5年間は定住フォロー期間となり、年1回程度の定住状況報告書提出や電話・訪問確認があります。
転出や離職など要件を満たさなくなった場合は返還義務が生じるため、ライフステージの変化で住所や就業状況が変わる際は必ず事前に自治体へ相談し、許可を得た上で行動しましょう。
フォローアップを活用すれば追加補助や子育て支援情報を得られることもあり、長期的な定住満足度向上につながります。
おすすめ自治体の支援金比較【2025】
同じ移住支援金制度でも、自治体が独自に上乗せする補助や子育て支援策を組み合わせると実質受給額が大きく変わります。
ここでは「総額が高い自治体」と「子育て支援が特に充実している自治体」をタイプ別に紹介し、家族構成やライフスタイルに合った地域を選びやすくしました。
高額支給の自治体例
山梨県北杜市では基本100万円に市独自の移住促進補助50万円、住宅取得補助最大100万円、リノベ補助50万円を併用でき、夫婦と子ども2人で起業を選択すると総額500万円超に達します。長野県飯山市も空き家改修費の3/4(上限150万円)を負担し、雪国手当として転入1年目に灯油代3万円を現金給付する独自策を展開しています。
さらに石川県珠洲市は復興人材を対象に世帯120万円+子ども加算各30万円に加え、家賃を3年間月1万円補助する制度を新設しました。
こうした自治体は転入後5年以上の定住や地域活動参加が条件となる場合が多いので、移住フェアやオンライン相談で要綱を確認し、世帯構成ごとに試算してから申請すると安心です。
子育て支援が充実した自治体例
徳島県神山町は子ども医療費を高校卒業まで全額助成し、保育料は第2子以降無料。移住支援金に加え、子ども1人あたり30万円の教育環境整備補助とICT端末の無償貸与を提供します。
福井県鯖江市では3歳未満に紙おむつ・ミルクを12ヶ月分支給し、小学校卒業まで給食費を半額補助されます。長崎県島原市は未就学児の家庭に毎月5,000円の子育て応援手当を5年間交付し、通学定期代も50%補助します。
これらの自治体は医療・教育・生活費を中長期でサポートするため、子どもの多い世帯ほど実質的な支援額と生活満足度が高まります。
夫婦で移住を成功させるコツ

資金面の不安を移住支援金で解消したら、次は移住後の暮らしを円滑にスタートさせるポイントを押さえましょう。
- 仕事探しとテレワーク活用
- 地域コミュニティへ溶け込む方法
- 夫婦の役割分担と家計設計
- 住まい選びとライフイベント
- 先輩移住者から学ぶ情報収集
以下でそれぞれ詳しく解説していきます。
仕事探しとテレワーク活用
地方でのキャリア形成は、地元企業への転職だけでなく現職を維持したままフルリモート勤務を続ける選択肢もあります。自治体やUIJターンセンターが開催するオンライン合同説明会に参加すれば、人事担当者と直接話して条件交渉が可能です。
人脈が乏しい時期は転職エージェントも併用し、非公開求人を含む複数社を比較表にまとめると夫婦間の意思決定が円滑になります。さらに副業を許可する企業を選べば、地域ビジネスや農業体験など複収入の芽も育ち、家計の安定とスキルアップを同時に図れます。
地域コミュニティへ溶け込む方法
移住直後は地域の祭りや清掃活動などの行事に自ら声を掛けて参加することが、顔と名前を覚えてもらう近道です。自治体主催の移住者交流会や子育てサロンでは同年代の家族と自然に情報交換ができ、子どもの友達づくりにも役立ちます。
挨拶やお裾分けなど小さな交流を積み重ねると、送迎や災害時の助け合いネットワークが短期間で構築され、生活の安心感が格段に高まります。SNSで地域イベントをシェアすると信頼も得やすく、仕事の紹介につながることもあります。
夫婦の役割分担と家計設計
移住前に平日の家事育児分担と収支計画を紙に書き出し、半年ごとに見直す仕組みを作ると想定外の負担増を防げます。固定費は支援金と自治体補助で賄い、変動費はキャッシュレスで可視化し月次で共有すると家計透明性が高まりストレスが減少します。
急な収入減や医療費発生に備え、生活防衛資金を6ヶ月分プールし、教育費は児童手当と積立投資で分散管理すると安心です。役割と数字を定期的に言語化して共有する文化を早期に定着させることが成功のポイントです。
住まい選びとライフイベント
候補地を3〜4エリアに絞り、通勤時間・通学動線・医療機関への距離を地図で可視化して物件を比較すると後悔が少なくなります。空き家購入+リノベは費用を抑えられますが入居まで6ヶ月以上かかる場合があるため、妊娠出産や就学など家族のライフイベントと工程表を擦り合わせることが肝要です。
新築や賃貸を選ぶ場合も住宅取得補助や家賃補助の申請タイミングが年度で異なるため、自治体担当者に確認してから契約しましょう。断熱性能や通信環境は光熱費と在宅勤務効率を左右します。
先輩移住者から学ぶ情報収集
地域おこし協力隊OBや先輩移住者のSNSコミュニティは、公式サイトに載らないリアルな情報が集まる貴重なデータベースです。質問する際は家族構成や移住希望時期を明示すると、具体的なアドバイスを得やすくなります。
学校や医療機関の評判、自治会費など細かな生活コストは実際の住民が最も詳しいため、複数ソースでクロスチェックして平均値を把握しましょう。成功談だけでなく失敗談も参考にするとリスク対策の優先順位が明確になり、移住計画の説得力が増します。
子育て世帯の移住計画ポイント
子どもの教育・医療インフラを把握し、初年度の家計を具体的に試算しておくと、移住後の想定外出費やサービス不足を未然に防げます。
ここではインフラ確認と家計試算、そして公的子育てサービスの活用方法を解説します。
教育・医療インフラの事前確認
転校や受診で困らないよう、学区配置・スクールバス・教員配置・通級指導の可否・放課後児童クラブの定員と利用料金を一覧で把握します。病院は小児科・産婦人科・救急指定の有無、夜間休日診療センターまでの距離を地図で確認し、災害拠点病院のバックアップ体制もチェックすることが大切です。
また、ICT環境を重視する場合は校内Wi‑Fi整備率やタブレット貸与の有無、オンライン診療対応クリニックの数も要確認。自治体HPの子育てマップと教育委員会に電話で最新空き状況を問い合わせ、実際に下見して通学路の安全性や医師の専門領域を現地で確認すると安心です。母子手帳交付窓口や予防接種実施医の予約待ち期間を早めに調べておくと、転入後の行政手続きが滞りなく進みます。
移住後1年の家計シミュレーション
世帯収入と想定支出を年間ベースで試算することで、支援金をどの費用に充当すべきかが明確になります。
以下は夫婦+子ども2人が地方都市へ移住した場合の一例です。
| 項目 | 月額 | 年間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 手取り収入 | 45万円 | 540万円 | 夫婦共働き |
| 住宅費 | 7万円 | 84万円 | 3LDK賃貸 |
| 食費 | 6万円 | 72万円 | 自炊中心 |
| 保育・学費 | 2万円 | 24万円 | 医療費無償 |
| 交通・ガソリン | 3万円 | 36万円 | 自家用車1台 |
| 通信・光熱 | 2.5万円 | 30万円 | 光熱費補助あり |
| 娯楽・交際 | 3万円 | 36万円 | 旅行年2回含む |
| 年間収支 | +258万円 | 支援金分は初期費用に充当 |
初年度は支援金で引っ越し費用と家具家電をまかない、黒字分を生活防衛資金として確保すると、予期せぬ支出にも対応できます。
地域子育てサービスの活用法
転校や受診で困らないよう、学区配置・スクールバス・教員配置・通級指導の可否・放課後児童クラブの定員と利用料金を一覧で把握します。病院は小児科・産婦人科・救急指定の有無、夜間休日診療センターまでの距離を地図で確認し、災害拠点病院のバックアップ体制もチェックすることが大切です。
また、ICT環境を重視する場合は校内Wi‑Fi整備率やタブレット貸与の有無、オンライン診療対応クリニックの数も要確認. 自治体HPの子育てマップと教育委員会に電話で最新空き状況を問い合わせ、実際に下見して通学路の安全性や医師の専門領域を現地で確認すると安心です。
母子手帳交付窓口や予防接種実施医の予約待ち期間を早めに調べておくと、転入後の行政手続きが滞りなく進みます。
まとめ
移住支援金は夫婦・子育て世帯にとって移住初年度の資金負担を大幅に減らす強力な制度です。最大100万円の世帯支援に子ども加算を合わせれば、住宅取得や引っ越し費用を実質0円に近づけられます。申請では対象求人での就業や5年間の定住などの要件を確実に満たす必要があります。
支援が手厚い自治体ほど独自補助や子育て環境が充実しているため、制度と暮らしやすさをセットで比較しましょう。
仕事・住まい・教育・コミュニティを具体的に計画し、家計シミュレーションと情報収集を徹底すれば、地方移住は家族の未来を豊かにする現実的な選択肢になります.
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介
ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介 ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント
ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点 ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説