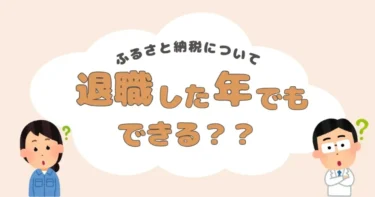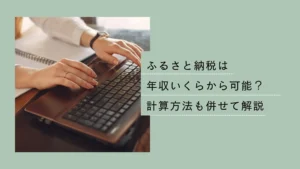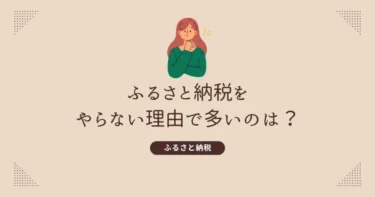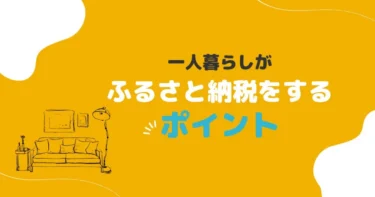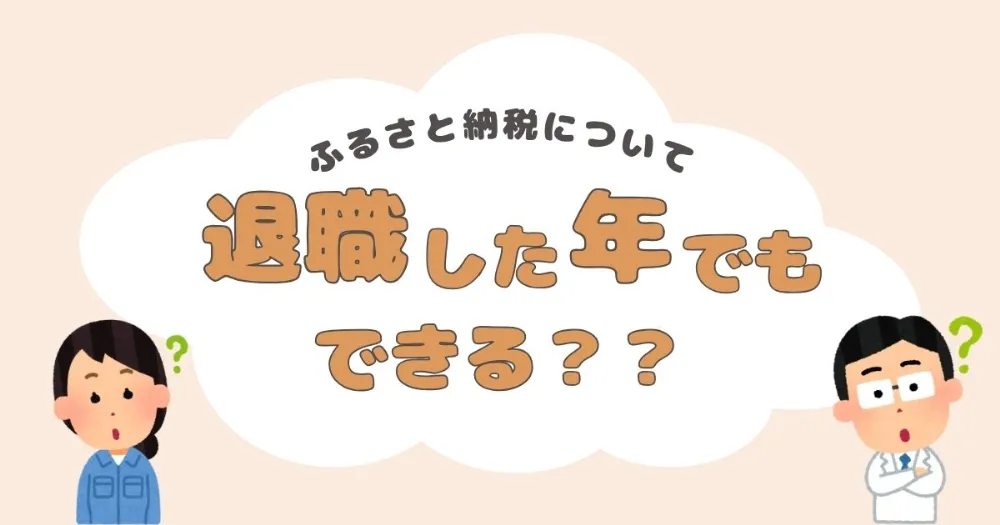
「今年退職したけれど、ふるさと納税をしても本当に得になるのだろうか?」
退職金課税や失業給付、年金受給のタイミングなどで収入構造が大きく変わると、控除上限額の試算に戸惑う人は少なくありません。上限を超えれば自己負担が増え、手続きの選択を誤ると確定申告で慌てることもあります。さらに「ワンストップ特例は使えるの?」「源泉徴収票が複数ある場合は?」といった書類面の疑問もつきまといます。
今回の記事では、退職した年でも賢くふるさと納税を活用するために「控除額の早見表と計算ステップ」「退職金・失業手当・公的年金を含めたケース別シミュレーション」「手続き上の落とし穴と回避策」をわかりやすく解説します。
読み終える頃には、自分の上限額を自力で算出し、安心して寄付を行えるようになります。
ふるさと納税は退職した年でもできる?基本ルールを確認

退職によって給与所得が途切れると「そもそも寄付できるのか」と不安になるかもしれませんが、制度上の制限はありません。寄付の受付は1月1日から12月31日まで通年で行われ、退職者であっても住民税と所得税の控除対象になり得ます。
ただし会社員が年末調整で自動的に控除を受けられた仕組みは使えなくなるため、控除額の試算と手続きを自分で管理する必要があります。
ここでは、以下の点について解説していきます。
- 退職しても寄付が可能な理由
- 退職年に寄付するメリット・デメリット
退職しても寄付が可能な理由
ふるさと納税は「所得があるかどうか」ではなく「その年に課税所得が生じるかどうか」で控除の有無が決まります。退職後に失業給付しか受け取らない場合でも、年初から退職日までに得た給与所得が残っていれば控除枠は確保できます。さらに、失業給付や公的年金は一定の計算式で課税対象になる場合があるため、「収入ゼロ」と思い込まず課税対象の有無を確認しましょう。
退職年に寄付するメリット・デメリット
メリットは、控除枠を超えない範囲であれば自己負担2,000円で返礼品を受け取れること、退職金が課税所得としてカウントされにくいケースでは控除枠が思ったより残る点です。
一方で、退職による急激な所得変動は試算を難しくし、枠を超えた場合は翌年以降への繰り越しができません。寄付後に追加納税が発生しないよう、控除上限の概算を二段階で見直す(退職時点と年末時点)のが安全です。
退職した年の控除上限額の計算方法

退職した年は、在職期間に応じた給与所得・退職所得・雑所得(年金等)が混在します。
そのため、総務省の「給与収入○円なら寄付上限×円」という早見表は使いづらく、手動シミュレーションが欠かせません。以下で代表的なケースを取り上げ、具体的な計算フローを解説します。
給与所得が途中で止まる場合の計算ステップ
給与収入が途中で途切れる場合の大まかな流れは次のとおりです。
- 退職までの給与総額を源泉徴収票で確認
- 給与所得控除を差し引き、「給与所得」を算出
- 各種所得控除(基礎・社会保険料・生命保険料など)を引き、課税所得を確定
- 課税所得をもとに住民税と所得税を見積もり、ふるさと納税の上限を算出
たとえば社会保険料は月末時点の加入状況で金額が変わり、退職月によって控除額が増減します。退職月が早いほど社会保険料控除が小さくなり、課税所得が増える点に留意してください。
退職金がある場合の課税所得の考え方
退職金は「退職所得控除」が手厚く、勤続年数に応じた計算式で控除されます。控除後の半額が課税対象となるため、同額の給与所得と比べて課税負担は軽くなります。ただし退職金の支給が翌年1月になると、その年の課税所得に含まれ、寄付上限計算にも影響するため支給時期を必ず確認しましょう。
失業給付や年金を含めたケース別シミュレーション
雇用保険の失業給付は非課税ですが、再就職手当や高年齢求職者給付金は課税対象になる場合があります。また65歳未満の老齢厚生年金は雑所得として課税されます。代表的な組み合わせと控除枠の傾向をまとめると次のとおりです。
| 収入パターン | 課税対象 | 控除上限の目安 |
|---|---|---|
| 給与+失業給付 | 給与のみ課税 | 給与所得ベースで算出(控除枠は小さめ) |
| 給与+年金(65歳未満) | 給与・年金課税 | 合算課税所得により中程度 |
| 退職金のみ | 退職所得 | 退職所得控除後の住民税額次第で控除枠は最小 |
自治体サイトのシミュレーターは給与所得の入力欄のみの場合があるため、該当しない所得区分は国税庁サイトの計算機やエクセルで補完するのがおすすめです。
ふるさと納税ワンストップ特例は退職年に使える?

ワンストップ特例は「寄付先が5自治体以内」「確定申告を行わない給与所得者であること」が大前提です。退職日に関係なく、翌年1月10日までに自治体へ申請書を提出すれば手続き完了ですが、年内に再就職せず源泉徴収票が発行されない場合、特例適用が認められない可能性があります。
利用条件と退職後の注意点
退職後にアルバイト収入を得ても給与所得者扱いになり、ワンストップ特例が有効になるケースがあります。ただし雇用形態により源泉徴収票発行が遅れることもあるため、年末までに発行タイミングを確認しておきましょう。
ワンストップ特例と確定申告のどちらを選ぶべきか
医療費控除や住宅ローン控除を受ける予定があり確定申告が必須なら、寄付件数に関係なくワンストップ特例は使えません。その場合は寄付ごとの受領証を集め、e-Taxの入力支援機能を利用して作業時間を短縮すると便利です。
確定申告で必要な書類と手続きの流れ
退職した年は複数社の源泉徴収票や退職所得の受給に関する書類が重なり、申告書類が増えがちです。提出漏れがあると控除額が正しく反映されず、寄付上限超過が後から判明するリスクもあります。
ここでは「書類をそろえる順序」と「提出時のチェックポイント」を解説します。
源泉徴収票が複数枚ある場合の扱い
複数枚の源泉徴収票は、給与所得を合算して一つの欄にまとめます。e-Taxの場合、PDF形式で添付すれば原本提出は不要ですが、紙申告ではコピーを含めてすべて添付する必要があります。控除額の自動計算がオフになっている場合は、合算金額を手入力しましょう。
退職金の源泉徴収票を添付するタイミング
退職金の源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票・特別徴収票)は、分離課税分として確定申告書第二表の該当欄に転記し、コピーを添付します。忘れると住民税で二重課税になる恐れがあり、ふるさと納税控除にも影響が出るため要注意です。
医療費控除や住宅ローン控除との優先順位
医療費控除や住宅ローン控除で所得が大きく減り、寄付上限が縮小するケースがあります。寄付額が上限を超えていないか、申告書作成後の「税額控除前所得税額」を見て再確認しましょう。
控除上限を超えないためのチェックリスト

上限超過は追加納税と自己負担増の原因になります。
ここで紹介する確認項目を使い、寄付前後のダブルチェックを習慣づけましょう。
寄付前に確認すべき3つの数字
- 年間課税所得の見込み(給与・年金・退職金を含む)
- 住民税額の概算(前年と同水準か要チェック)
- 既存の所得控除総額(医療費・社会保険料など)
たとえば上限ぎりぎりの寄付を予定している場合、年末に医療費がかさんで課税所得が減ると、控除枠が縮小して自己負担が発生します。必ず12月上旬時点で再計算し、余裕を持った額に調整しましょう。
寄付後にやるべきアフターフォロー
寄付証明書は自治体から順次届くため、ファイルを作成して到着日と寄付額を記録します。証明書未着のまま確定申告に進むと控除が認められず、後日更正手続きが必要になるので注意してください。
退職前・退職後に分けて考える最適な寄付タイミング
控除枠を最大限に活用するには「所得が高い在職中にまとめて寄付」「所得が見えにくい退職後に小分け寄付」の2パターンを検討します。それぞれのメリットとリスクを理解して選択しましょう。
退職前にまとめて寄付する戦略
年末まで在職の場合、給与所得が確定しているため上限額を精緻に算出できます。寄付をまとめれば返礼品が一度に届き在庫切れを避けやすい反面、退職金が同年に支給されると課税所得が急増し、上限を再計算する手間が発生します。
退職後に分散して寄付する戦略
退職後はアルバイト収入や再就職の予定が読めない場合があります。控除枠が小さく見積もられる6月〜10月頃は寄付を抑え、年末に所得をほぼ確定させてから不足分を寄付すると安全です。自治体のクレジット決済を活用すれば、12月31日23時59分まで寄付が反映されます。
よくある質問 | 退職年のふるさと納税Q&A
退職した年は、会社員時代とは税金の仕組みが少し変わるため、疑問を持つ方が多いです。
ここでは、退職者が特に迷いやすいポイントを一般的なケースとして紹介します。
Q1. 退職金もふるさと納税の「年収」に含まれますか?
A. 基本的には含まれますが、計算には注意が必要です。
退職金(退職所得)も、その年の所得としてカウントされるため、制度上はふるさと納税の控除上限額を押し上げる要因になります。
ただし、退職所得は税負担を軽くするために「分離課税」という特別な計算方法がとられており、給与所得とは分けて計算されます。そのため、単純に年収に足すだけでは正確な限度額とズレが生じることがあります。必ず「退職所得対応」のシミュレーションツールを使って目安を確認してください。
Q2. 失業保険(求職者給付)をもらっていますが、年収に含まれますか?
A. 原則として、年収には含まれません。
ハローワークから支給される失業保険(基本手当)は、税法上「非課税所得」として扱われます。税金がかからないお金なので、ふるさと納税の限度額計算の「年収」には含めないのが一般的です。
同様に、傷病手当金や遺族年金なども非課税ですので、これらを除いた「課税される収入(給与や退職金、公的年金など)」だけで計算しましょう。
Q3. 年の途中で退職した場合、確定申告は必要ですか?
A. 多くの場合、確定申告をした方がメリットがあります。
年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合は会社の「年末調整」を受けられないため、自分で確定申告をしないと払いすぎた所得税が戻ってこない可能性があります。
また、確定申告を行うと「ワンストップ特例制度」の申し込みは無効になります。ふるさと納税の分も合わせて確定申告書に記入する必要があるので、忘れずに申告することをおすすめします。
Q4. 住民税が「普通徴収(自分で納付)」になりましたが、控除はされますか?
A. 仕組み上は、問題なく控除されます。
在職中は給料から天引き(特別徴収)されていた住民税が、退職後は納付書での支払い(普通徴収)に切り替わることがあります。
この場合でも、正しく手続き(確定申告など)をしていれば、翌年の6月頃に届く住民税の納付書の金額から、寄付分が控除(減額)される仕組みになっています。納付書と一緒に届く「決定通知書」を見て、控除額が反映されているか確認しましょう。
退職年でも失敗しない!正確な計算&楽しみが広がる9サイト
退職した年のふるさと納税で最も重要なのは、「限度額の再計算」です。給与所得だけでなく、退職金や年金などが絡むと計算が複雑になるため、どんぶり勘定で寄付をするのは非常に危険です。
まずは、詳細な条件を入力できる「高精度シミュレーション」があるサイトで正確な上限額を把握しましょう。その上で、退職後の自由な時間を楽しめる「旅行・体験型」や、生活費を節約できる「高還元サイト」を選ぶのが賢い方法です。
退職のタイミングで利用するのにふさわしい、安心と楽しみを兼ね備えた9サイトを厳選しました。
| サイト名 | 退職イヤーのメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ふるなび | コイン還元で節約効果 | 生活費を浮かせたい人 |
| さとふる | 複雑な計算も対応< | 限度額が不安な人 |
| ふるラボ | 動画で失敗回避 | 実物をしっかり見たい人 |
| ニッポン | 厳選品でご褒美 | 退職祝いに良い物を探す人 |
| マイナビ | 10%還元で損を回避 | 計算ミスが怖い人 |
| ふるさと本舗 | 定期便で食費削減 | 家計を守りたい人 |
| au PAY | ポイント利用で手軽 | 手出し現金を抑えたい人 |
| ポケマル | 生産者との交流 | 食にこだわりたい人 |
| パレット | 旅行・体験が充実 | 自由な時間が増えた人 |
ここからは、それぞれのサイトが「退職前後のタイミング」になぜおすすめなのかを解説します。
ふるなび
収入が変化する時期だからこそ、少しでもお得に制度を活用したいもの。「ふるなび」なら、寄付額に応じて「ふるなびコイン」が還元され、Amazonギフトカードやdポイントに交換できます。
もし計算が難しくて限度額を少しオーバーしてしまったとしても、この還元分がクッションとなり、損をした感覚を和らげてくれます。家電製品も多いので、退職後の新生活準備にも最適です。
さとふる
退職した年は、給与所得だけでなく退職所得などが絡み、計算が複雑になりがちです。「さとふる」の「控除上限額シミュレーション(詳細版)」を使えば、源泉徴収票を見ながら正確な数値を算出できます。
「自分はいくらまで寄付できるのか?」という根本的な不安を解消できるため、失敗したくない退職イヤーの強い味方となります。
【ふるラボ】放送局運営の安心感
「ふるラボ」は、返礼品を動画で確認できるのが特徴です。退職の記念や贈り物として返礼品を選ぶ際、写真だけでは分からない質感やボリュームを映像でチェックできるのは大きな安心材料です。
「せっかくの記念なのに、思っていたのと違った」という失敗を未然に防ぎ、納得のいく品選びができます。
ふるさと納税ニッポン!
長年勤め上げた自分へのご褒美として、少し良いものを選びたいなら「ふるさと納税ニッポン!」です。編集部が厳選した、失敗のない逸品だけが揃っています。
「数は少なくていいから、本当に美味しいものが食べたい」という、量より質を重視する大人の選び方にぴったりのサイトです。
マイナビふるさと納税
「マイナビふるさと納税」は、寄付額の10%がAmazonギフトカードとして戻ってくるキャンペーンが魅力です。退職によって収入が減るタイミングだからこそ、現金に近い形で戻ってくるメリットは非常に大きいです。
計算ミスで少し損をしたとしても、10%の還元があればトータルでプラスに持っていける可能性が高く、リスクヘッジとしても優秀です。
ふるさと本舗
収入の変化に備えて、固定費を見直したい方には「ふるさと本舗」の定期便がおすすめです。お米やお肉が毎月届くように設定しておけば、スーパーでの買い出し費用を抑えられます。
Amazonギフトカードの高還元キャンペーンも頻繁に行われているため、賢く利用すれば家計の強い味方になります。
au PAY ふるさと納税
「現金をあまり減らしたくない」という方には、「au PAY ふるさと納税」がおすすめです。Pontaポイントで寄付ができるため、手持ちの現金を温存しながら制度を利用できます。
スマホ操作に慣れているauユーザーの方なら、入力の手間も省けて一石二鳥です。
ポケマルふるさと納税
退職して時間ができたら、食へのこだわりを深めてみるのも素敵です。「ポケマルふるさと納税」なら、全国の生産者と直接メッセージのやり取りができます。
「この野菜はどうやって食べるのが一番?」などと質問しながら、美味しい食材を取り寄せる体験は、単なる節税を超えた新しい趣味の時間になるかもしれません。
ふるさとパレット
退職後の最大の特権は「自由な時間」です。「ふるさとパレット」には、東急グループのホテル宿泊券や観光列車のチケットなど、平日の空いている時期にゆっくり使える体験型返礼品が充実しています。
モノをもらうだけでなく、「妻(夫)とゆっくり温泉に行く」といった思い出の時間に税金を使う。そんな贅沢な使い方ができるサイトです。
まとめ | 計算は慎重に、使い道は大胆に
退職した年のふるさと納税は、年収が確定する年末まで慎重に計算する必要があります。まずは「さとふる」などで正確な上限額を把握することから始めましょう。
しかし、上限額さえわかれば、あとは楽しむだけです。退職記念の旅行を「ふるさとパレット」で予約したり、「ふるなび」で欲しかった家電を揃えたりと、第二の人生のスタートを彩るために活用してみてください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介
ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介 ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント
ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点 ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説