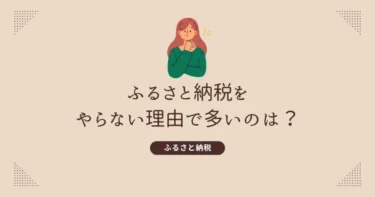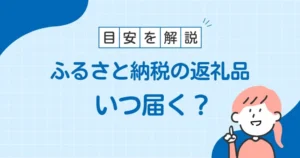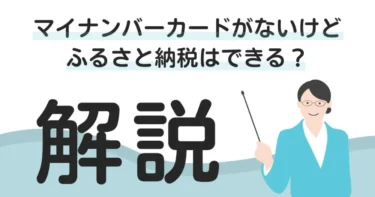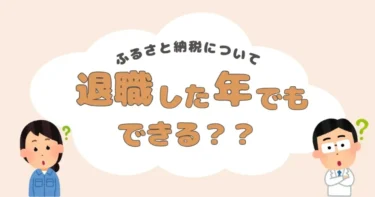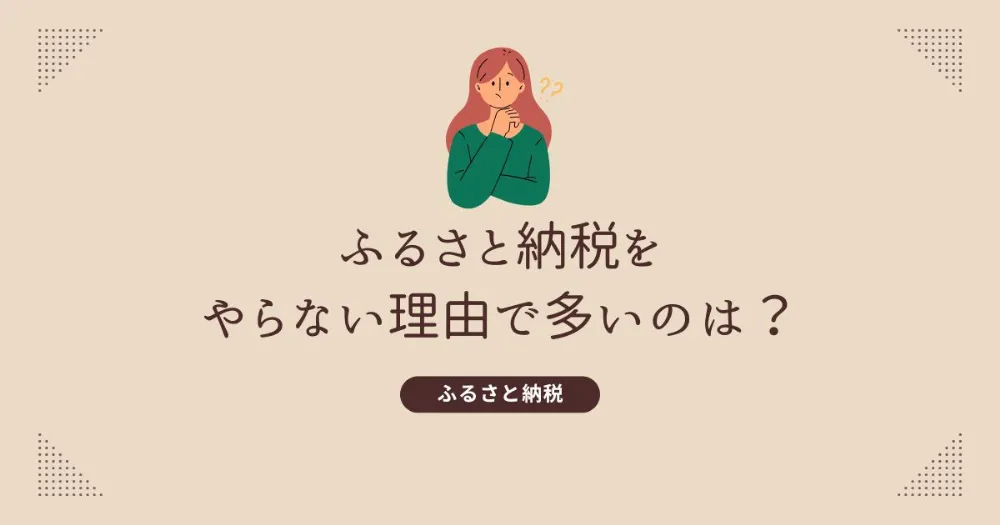
「ふるさと納税はお得らしいけれど、なぜか踏み切れない」。理由としては「時間がない」「手続きが面倒」「確定申告が必要そう」といった不安が目立ちます。実際は、会社員などで寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例で申告の手間を抑えられ、上限額はシミュレーションで目安をつかめます。一方で、先払いの負担や返礼品の到着時期、上限超過の注意などデメリットも理解しておきたいポイントです。
この記事では、「やらない理由」を誤解の観点から丁寧に解説し、今は見送った方が良いケースも示しつつ、今からでも始めやすい簡単ステップまで紹介します。検討中の方は参考にしてください。
- 「手続きが面倒くさそう」と感じて、まだ手を出せていない方
- 自分は「やらない方がいい人(損する人)」なのか確認したい方
- 失敗や損を絶対に避けて、一番簡単な方法で始めたい方
ふるさと納税をやらない理由とは?
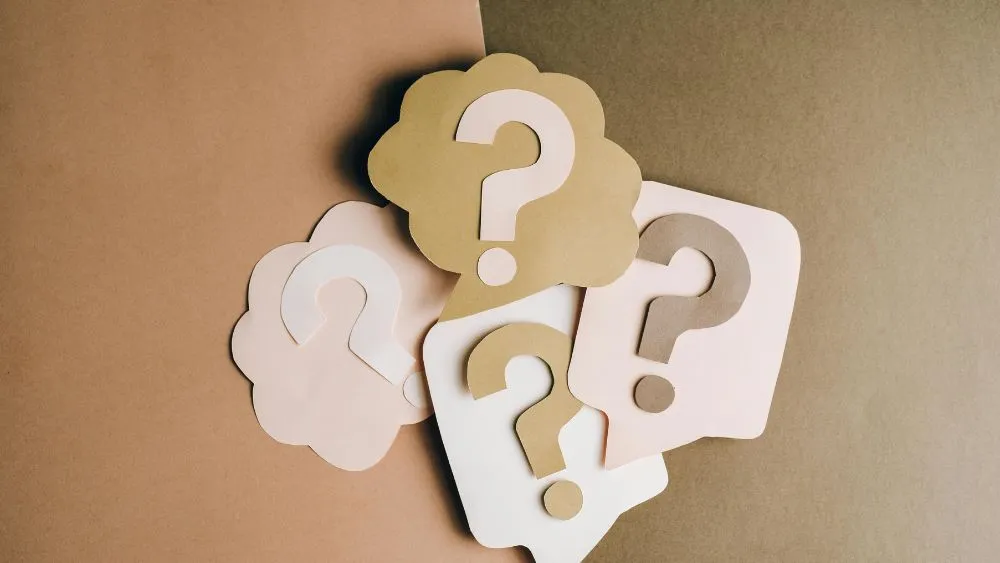
制度に興味はあっても、最初の一歩が踏み出せない人は少なくありません。多くは「時間がない」「手続きが難しそう」という不安からです。まずは代表的な理由を見直し、自分はどこでつまずいているのかを確かめましょう。
原因がわかると、次に取る行動が具体的になります。
- 手続きが面倒そうだからやらない
- 時間がなくて後回しにしてしまう
- 制度が複雑でよくわからない
- お金に余裕がないからできない
- 確定申告が必要になると思っている
上の項目はどれも工夫で軽くできる内容です。続く小見出しで、不安をやわらげる現実的な対処を解説します。
手続きが面倒そうだからやらない
ふるさと納税は「書類をたくさん書かないといけない」「複雑な申請が必要」というイメージが先行しがちです。確かに寄附後に申請書や本人確認書類を提出する必要がありますが、手順自体はシンプルです。
特に会社員で寄附先が5自治体以内ならワンストップ特例が利用でき、申請書に記入して返送するだけで控除が受けられます。最初は不安でも、実際にやってみると想像より簡単で、次回からはさらにスムーズに進められることが多いです。
時間がなくて後回しにしてしまう
「仕事や家事が忙しくて時間が取れない」と感じる人も多いですが、ふるさと納税の申し込み自体はオンラインで10分ほどで完了します。迷ってしまうのは膨大な返礼品から選ぶ段階が多いためです。あらかじめ「米」「肉」「日用品」など目的を決めて探すと短時間で選べます。
少額から寄附して流れを経験してみると、次回以降は手順を覚えてさらに時短できます。時間のハードルは思っているより低いものです。
制度が複雑でよくわからない
「仕組みが難しそうで理解できない」と感じる人は少なくありません。用語や控除の流れがややこしく見えるのも事実ですが、基本は「自己負担2,000円で返礼品を受け取り、残りは税金から控除される」という単純な仕組みです。
上限額をシミュレーションで確認して、その範囲で寄附をすれば大きな失敗はありません。複雑さに見える部分も、一度流れを知ってしまえば驚くほどシンプルに感じられます。
お金に余裕がないからできない
「今の生活費で精一杯だから余計な出費はできない」という気持ちは自然です。ただし、ふるさと納税はあくまで「翌年の税金を前払いする制度」なので、トータルで損をする仕組みではありません。返礼品を生活必需品にすれば、食費や日用品の支出を抑えられるケースも多いです。
もちろん無理をする必要はありませんが、少額からでも始められるため、自分のペースで利用を検討することが可能です。
確定申告が必要になると思っている
「確定申告をしないといけないから大変そう」と思う人も多いですが、すべての人が確定申告をする必要はありません。会社員で寄附先が年間5自治体以内ならワンストップ特例を使えて、申告は不要です。
自営業や副業がある人、医療費控除などで申告する人は確定申告が必要ですが、その場合も寄附金受領証明書を添付するだけで控除を受けられます。自分がどちらに当てはまるかを知るだけで、不安はぐっと和らぎます。
ふるさと納税をやらない人はどれくらいいる?

ふるさと納税は年々利用者が増えていますが、「まだやったことがない」という人も少なくありません。理由としては「制度が難しそう」「手続きが面倒そう」「家計に余裕がない」といった声がよく聞かれます。
やらない人が一定数いるのは決して珍しいことではなく、多くの人が同じように迷っているのです。まずはそうした声を知ることで、「自分だけが不安なのではない」という安心感を持ちながら検討を進められるはずです。
やらない人の割合と主な理由
調査やアンケートを見ると、ふるさと納税をまだ利用していない人は全体の3〜4割ほどいるといわれています。その理由として多いのは「制度や仕組みが難しそう」「返礼品を選ぶのに時間がかかりそう」「家計に余裕がなくて今はできない」といった声です。
特に初めての人ほど不安を感じやすく、制度を知らないことが心理的な壁になっているケースが目立ちます。しかし一度仕組みを理解すれば、多くの人が「思ったより簡単だった」と実感しており、最初の一歩を踏み出すかどうかが大きな分かれ目になっています。
利用者の体験談や実際の声
実際に始めた人の声には「シミュレーションで上限額がわかって安心した」「米や肉の定期便で生活費が助かった」「申請書を郵送するだけで終わって簡単だった」といった前向きな感想が多く聞かれます。一方で「年末ぎりぎりに申し込んだら書類が間に合わなかった」「上限を超えて寄附してしまい自己負担が増えた」という反省もあります。
こうした実例を知ると、成功のイメージと同時に注意点も理解でき、自分が行動するときの参考になります。ポジティブな体験とネガティブな体験の両方を把握しておくことで、安心して寄附に取り組めるようになります。
ふるさと納税をやらない理由は誤解が多い
ハードルの多くは、制度や手順を具体的に知らないことから生まれます。ワンストップ特例の条件、上限額の確認方法、寄附日の扱いなど要点だけ押さえれば、作業はぐっと軽くなります。
完璧を目指すほど動けなくなるため、まずは「小さく始める」を合言葉にしましょう。
ワンストップ特例で手続きは簡単
ふるさと納税をためらう理由のひとつに「確定申告が面倒」という声があります。しかし会社員などで寄附先が5自治体以内なら、ワンストップ特例を利用することで申告は不要になります。寄附後に届く申請書へ記入し、マイナンバー確認書類を同封して返送するだけで控除が反映される仕組みです。
申請期限は翌年1/10必着ですが、最近はオンライン対応の自治体も増えており、スマホで数分で済ませられる場合もあります。最初は複雑に思えても、実際にやってみると想像以上に簡単だと感じる人が多い制度です。
少額でもできるので無理なく始められる
「まとまったお金がないと利用できない」と思われがちですが、ふるさと納税は1万円未満の少額からでも始められます。上限額に満たない金額であっても問題はなく、返礼品を生活に役立つ米や日用品にすれば家計の節約にもつながります。
小さな金額から始めることで、制度の流れや申請の仕組みを体験でき、翌年からは安心して寄附額を調整できるようになります。無理をせずに「できる範囲」で試すことが、長く続けるための第一歩です。
控除シミュレーションで安心して寄附できる
「寄附額の上限がわからないから不安」という人も多いですが、主要なポータルサイトにあるシミュレーションを使えば数分で目安が出せます。必要なのは年収や家族構成などの基本情報だけで、計算は自動で行われます。目安の9割程度を上限にしておけば、年末の収入変動や控除の追加があっても安心です。
数字が出ることで漠然とした不安が解消され、寄附額を決めるときの迷いも少なくなります。まずはシミュレーションで全体像を把握することが、安心して始めるための一歩になります。
ふるさと納税のデメリットも理解しておこう

ふるさと納税はお得な制度ですが、良い面だけに目を向けてしまうと「思っていたのと違う」と感じることもあります。出費のタイミングや返礼品の到着時期、上限額を超えた場合の扱いなど、事前に知っておけば避けられる注意点があります。
デメリットを理解したうえで取り組むことで、安心感を持って長く続けられるようになります。
一時的に出費が必要になる
寄附金は年内に支払うため、控除が反映されるのは翌年の税金です。つまり一度は家計からお金が出ていく仕組みになっています。生活費に余裕がない月に一気にまとめて寄附すると負担感が大きくなるので、少額で分けて寄附する、ボーナスや臨時収入の後に行うなどの工夫が大切です。自分に合った時期と金額を選べば、出費が重荷にならずに制度を上手に活用できます。
返礼品の到着が遅れることもある
ふるさと納税の返礼品は自治体や品目によって発送までの期間が異なり、特に人気商品や季節限定品は到着まで数か月かかることもあります。冷蔵・冷凍品や定期便は保管場所や消費ペースを考えておかないと、受け取った後に困る場合があります。
注文前に発送時期や賞味期限を確認し、生活リズムに合った返礼品を選ぶと安心です。届くまでの時間も楽しみのひとつと考えれば、待つ期間も前向きに感じられます。
上限額を超えると自己負担が増える
ふるさと納税は「自己負担2,000円」と言われますが、それは上限額の範囲内で寄附した場合に限られます。上限を超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります。複数のサイトや自治体に寄附する際は合計金額を忘れずに管理することが重要です。
最初にシミュレーションで目安を出し、寄附ごとに合計を記録しておくと安心です。少し余裕を持った金額に抑えることで、予期せぬ超過を防ぎやすくなります。
本当にふるさと納税をやらない方が良い人
ふるさと納税は多くの人にとってお得で便利な制度ですが、すべての人に無条件で向いているわけではありません。生活状況や税金の仕組みによっては、今は無理に利用しない方が安心できる場合もあります。
ここでは、制度を利用しない方が良いケースを整理し、自分に合うかどうかを見極める参考にしてみてください。
確定申告をどうしても避けたい人
寄附先が6自治体以上になる、住宅ローン控除や医療費控除を受ける、給与収入が2,000万円を超えるなどの場合は確定申告が必須になります。電子申告やスマホ申請など便利な方法も整っていますが、どうしても申告そのものに抵抗がある人にとっては心理的な負担が大きく感じられるでしょう。
その場合は、まずは制度を理解するだけに留め、無理なくできるタイミングが来てから始めるのも賢い選択です。
収入が少なく控除の対象外になる人
住民税や所得税が発生しない水準の収入の場合、ふるさと納税をしても控除は受けられません。返礼品は届きますが、自己負担2,000円ではなく全額が自己負担になってしまいます。
生活費に余裕がないときに利用しても負担が増えるだけなので、課税が発生するようになってから取り組むのが安心です。制度は毎年利用できるため、焦らずタイミングを待てば問題ありません。
寄附金の出費自体が負担になる人
制度は翌年の税で還元されますが、寄附の時点では一時的に現金やカードの支出が必要です。毎月の生活費や教育費のやりくりで精一杯なときに無理をして寄附をすると、かえって家計の不安につながることもあります。
まずは暮らしを安定させることを優先し、余裕が生まれたときに少額から始めれば十分です。ふるさと納税は義務ではなく自由に選べる制度なので、自分のペースで取り入れれば大丈夫です。
ふるさと納税は結局やった方が得

「得」と言い切ると強い印象になりますが、制度の条件を守れば自己負担2,000円で返礼品と控除を受けられる点は事実です。
家計の実利に加えて地域貢献の実感も得られるため、多くの人にとって「やる価値が高い制度」といえます。お金と気持ちの両面で満足を得やすいのが魅力です。
自己負担2,000円で返礼品が届く仕組み
ふるさと納税は、寄附額から自己負担2,000円を除いた金額が翌年の税金から控除される制度です。つまり、上限額の範囲で寄附すれば実質2,000円の負担だけで返礼品を受け取れることになります。控除はワンストップ特例なら翌年度の住民税に反映され、確定申告をした場合は所得税の還付と住民税の軽減という形で戻ってきます。
仕組みを理解すると「本当に得なのか」という疑問が解消され、安心して利用できるようになります。
税金が控除されて家計の負担も軽くなる
控除の効果は翌年の住民税や所得税に直接反映されるため、家計の負担を確実に減らすことができます。さらに、返礼品を米や日用品など生活に直結する品にすれば、支出を減らす実感を持ちやすくなります。
節約につながるだけでなく「お得に家計を回せている」という満足感も得られるため、制度を前向きに続けるモチベーションにもつながります。
地域を応援できる社会的意義がある
ふるさと納税は単なる節税の仕組みではなく、寄附先の自治体や生産者を直接応援できる制度です。子育て支援や教育、災害復旧など、使い道を自分で選べる点も魅力です。さらに特産品を受け取ることで、地域の良さを感じたり新しい魅力を知るきっかけにもなります。
家計のメリットを得ながら、社会に貢献できる喜びを味わえることは、ふるさと納税ならではの大きな魅力です。
今からでも間に合う!ふるさと納税の簡単ステップ
思い立ったときに始められる制度です。順序を決めて進めれば迷いません。短時間の作業を積み重ねて、確実に完了させましょう。
- 控除上限額をシミュレーションで確認
- ポータルサイトで寄附先と返礼品を選ぶ
- ワンストップ特例を使って申請書を提出
- 年末駆け込みで注意すべきポイント
上の流れで進めると、迷いが少なく失敗もしにくくなります。最後に期限と寄附日の扱いだけ再確認して、安心して申し込みへ進みましょう。
控除上限額をシミュレーションで確認
最初にやるべきは、自分が寄附できる上限額の確認です。年収や扶養家族の有無などを入力するだけで目安額が表示され、作業は数分で終わります。算出した額いっぱいまで寄附してしまうと年末の収入変動や控除の追加で超過する恐れがあるため、結果の9割程度を目安に設定しておくと安心です。メモや表に残しておけば、複数の自治体に寄附するときも合計額を管理しやすくなります。
ポータルサイトで寄附先と返礼品を選ぶ
次はポータルサイトで寄附先と返礼品を決めます。数多くの候補から選ぶ際には「食費の節約につながる米や肉」「日常的に使う日用品」などテーマを先に決めると迷いにくいです。レビューや発送時期、量や賞味期限を確認すると、到着後の不便を避けられます。人気返礼品は年末に在庫切れになることもあるため、早めにチェックしてお気に入りに登録しておくとスムーズに申し込みできます。
ワンストップ特例を使って申請書を提出
寄附ごとに自治体から送られるワンストップ特例申請書に記入し、マイナンバー確認書類を添えて返送します。提出期限は翌年1/10必着なので、年末の寄附は特に注意が必要です。郵送の場合は年末年始の配送遅延も考慮し、余裕を持って投函するのがおすすめです。最近はオンライン申請に対応する自治体も増えており、スマホから簡単に完了できるケースもあるため、自分が寄附した自治体の案内を確認すると安心です。
年末駆け込みで注意すべきポイント
12月は寄附が集中する時期で、返礼品の在庫切れや発送遅延が起こりやすくなります。さらに、寄附日は「クレジット決済が完了した日」など決済方法によって扱いが異なり、12/31ぎりぎりだと翌年扱いになる可能性もあります。安全に控除を受けるためには、少なくとも数日前までに寄附を済ませるのが理想です。申請書も期限を守れるよう、年末に駆け込む場合はオンライン申請を優先すると失敗が減ります。
「面倒・不安」を解消!やらない理由をなくす9サイト
ふるさと納税をやらない理由の多くは、「品物を選ぶのが大変」「手続きが複雑そう」「損をしそう」といったものです。
しかし、今は「返礼品選びを後回しにできる機能」や、スマホだけで完結する「ワンストップ特例申請」、さらに「ポイント還元」のおかげで、これらのハードルは完全に解消されています。
「これなら私にもできる」と思える、初心者や慎重派に優しい9サイトを厳選しました。
| サイト名 | 「やらない理由」を解決 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ふるなび | 「あとから選べる」で期限の焦りなし | 選ぶのが面倒な人 |
| さとふる | アプリ申請で書類不要 | 手続きが億劫な人 |
| ふるラボ | 動画で失敗リスク減 | 写真詐欺が怖い人 |
| ニッポン | 丁寧な解説と厳選品 | 仕組みがよく分からない人 |
| マイナビ | 10%還元で確実に得 | 損をするのが嫌な人 |
| ふるさと本舗 | 高還元で「損」の不安を一掃 | 現金に近いメリットが欲しい人 |
| au PAY | ポイント払いでハードル減 | 身銭を切りたくない人 |
| ポケマル | 生産者と話せる安心感 | 怪しい業者を避けたい人 |
| パレット | 体験型でモノが増えない | 部屋を散らかしたくない人 |
ここからは、それぞれのサイトがどのように「やらない理由」を解決してくれるのかを解説します。
ふるなび
「数万点の中から選ぶなんて無理!」という理由で諦めているなら、「ふるなび」のカタログ機能が解決します。とりあえず寄付をしてポイントに変えておけば、返礼品選びは有効期限なしでいつでもOK。
さらにコイン還元もあるため、「損をするかも」という金銭的な不安も同時に解消してくれます。
さとふる
「役所の手続きなんて面倒くさそう」というイメージがあるなら、「さとふる」を見てみてください。アプリを使えば、確定申告不要の「ワンストップ特例申請」がスマホだけで完結します。
封筒を用意したりポストに行ったりする必要がないため、ズボラな方でも寝転がりながら手続きが終わります。
【ふるラボ】放送局運営の安心感
「変なものが届いたら嫌だ」と疑っている方には、「ふるラボ」がおすすめ。放送局が運営しており、返礼品を動画で紹介しているため、情報の信頼性が段違いです。
「よく分からない怪しいサイト」ではなく、テレビのような感覚で安心して利用できるのが強みです。
ふるさと納税ニッポン!
「そもそも制度がよく分からない」という理由で避けているなら、解説が丁寧な「ふるさと納税ニッポン!」が最適です。
初心者向けのガイドが充実しており、さらにプロ厳選の返礼品しか載っていないため、知識ゼロで始めても失敗しようがありません。
マイナビふるさと納税
「2,000円の自己負担すら惜しい」と感じるなら、「マイナビふるさと納税」です。寄付額の10%がAmazonギフトカードで戻ってくるため、2万円以上寄付すれば自己負担分は完全にペイできます。
「やると損」どころか「やらないと損」であることを、数字で証明してくれるサイトです。
ふるさと本舗
「ふるさと本舗」は、Amazonギフトカード還元のキャンペーンが非常に強力です。時期によっては大手サイト以上の還元率を叩き出すことも。
「どうせやるなら極限まで得したい」という、徹底した損得勘定をお持ちの方でも満足できるスペックを持っています。
au PAY ふるさと納税
「手元の現金を減らしたくない」という理由で躊躇しているなら、「au PAY ふるさと納税」でPontaポイントを使いましょう。余っているポイントで税金を払えるので、お財布の痛みはゼロ。
「ポイント消化のついで」という軽い気持ちで始められるのが魅力です。
ポケマルふるさと納税
顔の見えない相手との取引が不安なら、「ポケマルふるさと納税」です。生産者と直接メッセージのやり取りができるため、まるで近所の農家さんから買うような安心感があります。
「怪しい業者は嫌だ」という警戒心の強い方でも、ここなら安心して利用できます。
ふるさとパレット
「モノが増えるのが嫌」というミニマリスト志向の方には、「ふるさとパレット」の体験型返礼品が正解。旅行や食事のチケットなら、部屋のスペースを圧迫しません。
「邪魔になる」というやらない理由を、スマートに解消してくれるサイトです。
ふるさと納税を「やらない」に関するよくある質問
Q1. 本当に自己負担2,000円だけで済むんですか?
A. はい、本当です。
ご自身の「控除限度額」の範囲内で寄付を行えば、寄付総額から2,000円を引いた全額が、翌年の税金から控除(または還付)されます。
ただし、限度額を超えて寄付してしまうと、超えた分は自己負担になるため、事前のシミュレーションが必須です。
Q2. 確定申告は絶対に必要ですか?面倒くさいのですが…
A. いいえ、必ずしも必要ではありません。
会社員の方で、1年間の寄付先が5自治体以内であれば、「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が不要になります。
さらに、一部のサイトではアプリで申請が完結するため、書類の郵送すら不要です。
Q3. 「やらない方がいい人」ってどんな人ですか?
A. 主に以下のような方は、メリットがない(または薄い)ため、無理にやる必要はありません。
・年収が低く、所得税・住民税を払っていない方(扶養内パートなど)
・住宅ローン控除などで、すでに税金が全額控除されている方
・年収に対して寄付限度額が極端に低い方(手間の方が上回る可能性があるため)
Q4. 手続きを忘れたらどうなりますか?
A. 控除の手続き(ワンストップ特例または確定申告)を忘れると、税金の控除が受けられず、寄付金はただの「寄付」になります。
ただし、確定申告は5年前まで遡って行うことができるため、もし忘れてしまっても後からリカバリーは可能です。
まとめ | 「食わず嫌い」は損!ツールを使えば誰でも簡単・お得に
ふるさと納税をやらない理由の9割は、「面倒くさい」「よく分からない」という思い込みによるものです。しかし実際は、アプリ申請やカタログ機能など、面倒な手間を省くツールが充実しており、誰でも簡単に始められるようになっています。
「やらない方がいい人(税金を払っていない人)」を除けば、ほとんどの人にとってふるさと納税は「やらないと損」な制度です。ぜひ、今回ご紹介した初心者向けのサイトを活用して、重い腰を上げ、お得な返礼品を受け取ってください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介
ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介 ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント
ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点 ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説