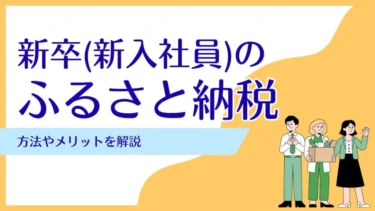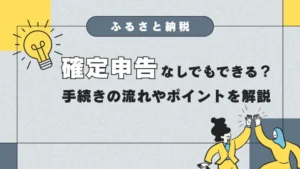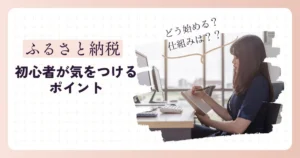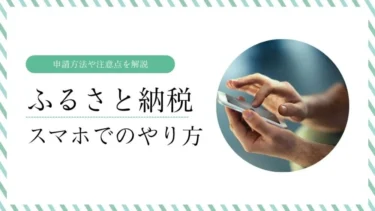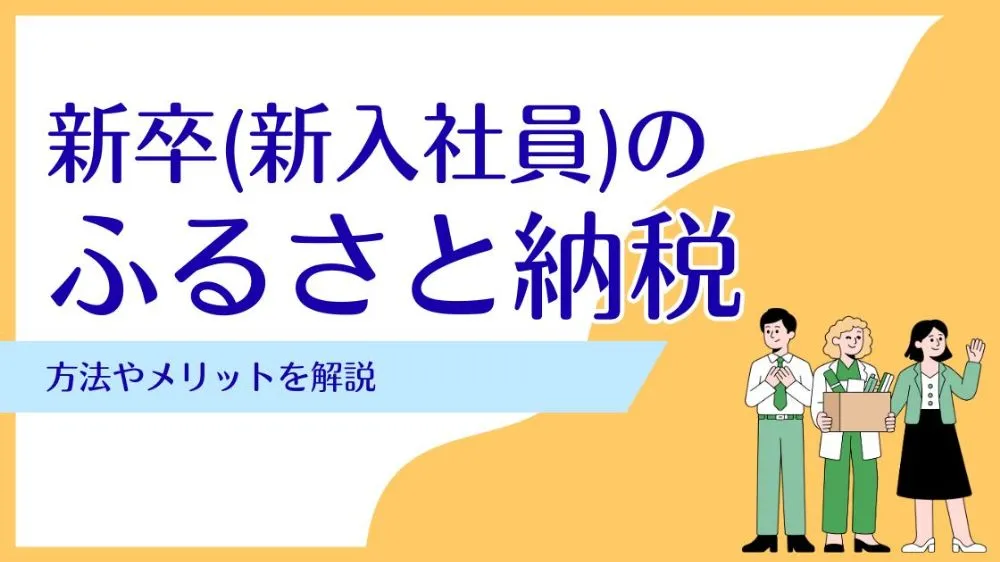
社会人になったばかりで、「ふるさと納税って自分もできるの?」「収入が少なくても意味あるの?」と迷う方は多いのではないでしょうか。新卒の方でも給与所得が発生すれば、ふるさと納税の利用が可能になります。
この記事では、新入社員がふるさと納税を始められるタイミングや手続きの流れ、注意しておきたいポイントをわかりやすく解説します。控除額の目安やおすすめの返礼品も紹介するので、初めての方でも安心して取り組めます。
初任給を受け取ったばかりの方や、ふるさと納税に興味はあるけれど難しそうと感じている方は、ぜひ参考にしてください。社会人生活の第一歩として、ふるさと納税を上手に活用できるようになります。
- 源泉徴収票がまだないけど、限度額を知りたい
- 難しい書類手続きはナシで、スマホだけで済ませたい
- 一人暮らしの生活費を浮かせたり、Amazonギフト券が欲しい
- 初任給やボーナスで、実家の親に美味しいものを贈りたい
新卒でもふるさと納税はできる?

社会人になったばかりでも、ふるさと納税は利用できます。税金を納めている人であれば対象となるため、新卒の方も給与所得が発生した時点で寄付を行うことが可能になります。ただし、学生時代のアルバイト収入のみでは対象外となるケースもあり、条件を正しく理解しておくことが大切です。
ふるさと納税ができる基本条件とは
ふるさと納税は、寄付金額に応じて所得税と住民税が控除される制度です。対象となるのは「課税所得がある人」で、会社員として給与を受け取り、税金を納めている場合に利用できます。控除額は年収や家族構成、扶養の有無によって変わり、たとえば独身で年収200万円ほどなら控除上限は1万円〜2万円程度が目安です。
寄付の対象期間は1月1日から12月31日までで、その年の所得に対して控除が適用されます。新社会人の1年目は、まず自分の課税状況を把握してから寄付を行うと安心です。
給与所得者として対象になるタイミング
新卒の方がふるさと納税を始められるのは、初めての給与を受け取ってからになります。給与から所得税が天引きされている時点で、税金を納めている状態になるため、制度の対象となります。 寄付の対象期間は1月〜12月で、寄付した金額がその年の所得に応じて控除の対象となります。
4月入社の場合、6月以降に給与が安定してから寄付を検討すると、より正確に上限額を判断できます。 初年度は年収が確定していないため、控除上限を少し低めに見積もっておくと安心です。年末に近づくほど実際の収入が把握しやすくなるため、10月以降に寄付を行う人も増えています。
アルバイト・パート収入の場合はどうなる?
学生時代からアルバイトで収入を得ていても、課税される水準に達していなければ、ふるさと納税の控除対象にはなりません。 一般的に、所得税の課税が始まるのは年収103万円を超えた場合、住民税の課税はおおむね100万円前後からとなります。この基準を下回ると、そもそも税金が発生しないため控除を受けられません。 一方で、社会人としてフルタイム勤務をしている、またはアルバイトでも年間収入が課税ラインを超えている場合には、ふるさと納税を利用できます。 次の表は、おおよその課税ラインと利用可否の目安です。
| 勤務形態 | 年間収入の目安 | ふるさと納税の利用可否 |
|---|---|---|
| 学生アルバイト(週2〜3日) | 〜100万円未満 | 利用できない(非課税) |
| 社会人(正社員) | 180万円〜 | 利用できる |
| パート勤務(フルタイム) | 120万円〜 | 利用できる場合がある |
このように、判断の基準は「税金を納めているかどうか」です。自分の収入額が課税対象に該当するかを確認してから手続きを行うと、無駄のない寄付ができます。
新卒がふるさと納税を始めるタイミング

ふるさと納税は1年中いつでも寄付ができますが、給与が安定してから始めるのが理想です。初任給後すぐに寄付しても問題はありませんが、年収が確定していないうちは控除額を誤るおそれがあるため、慎重に判断することが大切です。
初任給を受け取ったら利用可能になる理由
初任給を受け取ると、所得税が天引きされるようになります。この時点で税金を納めているため、ふるさと納税の対象になります。 ただし、新卒1年目は年収の見通しが立ちにくいため、寄付額を決める際はシミュレーションを活用するのが安心です。
ふるさと納税サイトでは年収・家族構成・扶養の有無を入力するだけで上限額を計算できます。特に6月以降は給与も安定しやすく、寄付の検討に適した時期といえます。
年末ギリギリでも間に合う?時期の目安を解説
ふるさと納税は12月31日までに寄付が完了していれば、その年分の控除対象となります。年末ギリギリでも申し込み自体は可能ですが、返礼品の在庫切れや申請書類の発送遅延が発生しやすいため、10月〜12月上旬の申し込みが理想です。
また、ワンストップ特例の申請書提出期限は翌年1月10日頃までとなるため、年末に寄付をする際は書類の準備を早めに進めましょう。
確定申告とワンストップ特例の違いを理解しよう
ふるさと納税の控除を受けるには「確定申告」または「ワンストップ特例制度」のいずれかの手続きが必要です。会社員の新卒であれば、確定申告をしなくても済むワンストップ特例を利用するのが一般的です。
この制度は、寄付先が5自治体以内であれば申請書を提出するだけで完了します。一方、転職や副業などで複数の収入源がある場合は、確定申告によって控除を受ける必要があります。どちらの方法を取るかを事前に確認しておくと安心です。
新入社員がふるさと納税をするメリット

新卒でふるさと納税を始めることで、返礼品を受け取るだけでなく、社会人として税金の仕組みを理解するきっかけにもなります。節約や生活の充実につながるだけでなく、地域貢献という形で社会との関わりを感じられる点も大きな魅力です。
お得に返礼品がもらえる仕組み
ふるさと納税は、自己負担2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除される制度です。たとえば3万円を寄付した場合、実質負担は2,000円で済み、残りは翌年の税金から差し引かれます。 年収が200万円程度の新卒でも、寄付金上限の目安は1万円前後となり、気軽に始めやすい金額です。食品や日用品、日持ちする冷凍食材などを選べば、生活費の節約にもつながります。
初めてのふるさと納税では、「毎日使うもの」「すぐ消費できるもの」を選ぶのがポイントです。家計への負担を抑えながら実感できるお得さが、最大の魅力といえるでしょう。
節税しながら地域貢献ができる
ふるさと納税の大きな魅力は、寄付先を自分で選べる点にあります。出身地や応援したい地域を選ぶことができ、寄付金の使い道も「子育て支援」「教育」「防災」「医療」などから選択可能です。 単なる節税制度にとどまらず、自分の納めたお金がどのように地域に役立っているかを実感できる仕組みになっています。寄付先自治体のホームページで使途報告を確認できる場合もあり、「社会の一員として支えている」という実感を得やすいのが特徴です。
税金を“取られるもの”ではなく、“活かすもの”として考えられるようになる点も、新卒のうちに経験しておきたいメリットのひとつといえます。
社会人として税金の仕組みを学べる
社会人になって初めて給与明細を見ると、「所得税」「住民税」などの項目に戸惑う方も多いはずです。ふるさと納税を通じて、これらの税金がどのように控除されるのかを体験的に理解できます。 寄付証明書の提出やワンストップ特例申請の手続きを行うことで、税金や行政手続きへの理解が自然と深まります。こうした経験は、将来的に確定申告や節税を考える際にも大いに役立ちます。
さらに、寄付金控除の流れを知ることで、自分の収入や支出を見直すきっかけにもなります。税金の仕組みを“知るだけ”でなく“体感する”ことで、社会人としての金銭感覚が磨かれるでしょう。
新卒がふるさと納税をする際の注意点
初めてふるさと納税を行う場合は、控除上限額や申請期限、提出書類などに注意が必要です。特に新卒1年目は年収が確定していないため、寄付金額を誤ると控除を超えてしまうことがあります。
制度の仕組みを理解したうえで、無理のない範囲で行うことが大切です。
控除上限額を超えないように注意
ふるさと納税では、年収や家族構成などによって控除上限額が決まります。この上限を超えて寄付しても、超過分は控除されないため自己負担が増えてしまいます。 目安として、独身で年収250万円の場合の控除上限は約2万円前後です。ポータルサイトのシミュレーションツールを使えば、年収や扶養条件を入力するだけで簡単に上限額を確認できます。
初年度は賞与や昇給の見通しが不明なことが多いため、ギリギリまで寄付せず、少し控えめに設定しておくのが安全です。控除額は翌年の住民税で反映されるため、節税効果を感じられるのは翌年6月以降となります。
ワンストップ特例の申請期限と提出方法
会社員の多くは確定申告を行わず、「ワンストップ特例制度」を利用します。この制度を使えば、寄付先が5自治体以内であれば確定申告をせずに控除を受けられます。 ただし、申請期限は翌年1月10日までで、これを過ぎると無効になります。申請書にはマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類のコピーを添付し、寄付した自治体へ郵送します。
最近では、マイナポータル連携によるオンライン申請に対応する自治体も増えており、スマートフォンから簡単に提出できる場合もあります。郵送の手間を省きたい方は、電子申請対応の寄付先を選ぶと良いでしょう。
ボーナスや転職がある場合の注意点
新卒1年目でも、ボーナス支給や転職などで年収が変動するケースがあります。年収が上がれば控除上限も増えますが、減収となった場合は超過寄付になる可能性があるため注意が必要です。 転職をした場合、複数の勤務先から源泉徴収票が発行されるため、ワンストップ特例を利用できず確定申告が必要になることもあります。勤務先が変わる可能性がある方は、年末に実際の収入を確認してから寄付すると安全です。
また、ボーナスを含めた年収が確定するのは年末に近いため、秋以降に寄付を行うと上限額の見誤りを防げます。自分の収入状況を定期的に見直しながら、柔軟に寄付額を調整していく意識が大切です。
新卒がふるさと納税をする手順

ふるさと納税は手続きが複雑に見えるかもしれませんが、実際は3つのステップで完結します。
大まかに「控除上限額の確認」「返礼品の選択」「申請手続き」の流れを把握しておけば、初めての新卒でもスムーズに進められます。
- 手順① 寄付金控除上限額をシミュレーションする
- 手順② ポータルサイトで返礼品を選ぶ
- 手順③ ワンストップ特例または確定申告を行う
それぞれの手順を順番に進めるだけで、安心してふるさと納税を完了できます。
ここでは、初心者にもわかりやすく具体的に解説します。
手順① 寄付金控除上限額をシミュレーション
最初に、自分がどのくらい寄付できるかを確認します。控除上限額は年収や家族構成によって変動し、年収200万円の場合はおおむね1万円前後、300万円なら3万円程度が目安です。 シミュレーションは、さとふる・ふるなび・楽天ふるさと納税などのポータルサイトで簡単に行えます。入力するのは「年収」「家族構成」「扶養の有無」など数項目のみで、数分で結果がわかります。
初年度は昇給やボーナスの見通しが不明なことも多いため、少し余裕を持った金額設定にしておくと安心です。上限を超えると控除されないため、無理のない範囲で寄付額を決めましょう。
手順② ポータルサイトで返礼品を選ぶ
控除上限を確認したら、ふるさと納税サイトで返礼品を選びます。全国の自治体が掲載しており、食品、日用品、家電、体験型サービスなどジャンルは多岐にわたります。 一人暮らしを始めた新卒には、冷凍食品やお米、トイレットペーパーなど、生活に直結する実用的な品がおすすめです。消費しやすく、節約にもつながります。
また、寄付金の使い道を選べる自治体も多く、教育・医療・防災など自分の関心分野を応援することもできます。地域の特色や社会貢献の視点で選ぶと、返礼品以上の価値を感じられるでしょう。 返礼品を選ぶ際は、配送時期や発送状況も事前に確認しておくと安心です。特に年末は注文が集中するため、余裕を持った申し込みを心がけましょう。
手順③ ワンストップ特例または確定申告を行う
寄付をしたら、控除を受けるための手続きを忘れずに行います。会社員の新卒の場合、一般的には「ワンストップ特例制度」を利用できます。この制度を使えば、確定申告を行わなくても控除が受けられます。 申請方法は、寄付時に自治体へ申請書を請求し、寄付後に届く申請書に必要事項を記入して返送するだけです。マイナンバーカードや本人確認書類(運転免許証など)のコピーを添えて、翌年1月10日までに自治体へ送付します。
また、近年はマイナポータルを使ったオンライン申請にも対応する自治体が増えており、スマートフォンから簡単に提出できます。郵送よりも手軽なため、忙しい社会人にとって便利な方法です。 一方で、寄付先が6自治体を超える場合や、転職・副業などで収入が複数ある場合は確定申告が必要になります。寄付金受領証明書を添付し、2月16日〜3月15日の間に税務署へ提出しましょう。どちらの方法でも、手続きを完了させて初めて控除が適用される点を忘れないようにしてください。
新卒におすすめのふるさと納税返礼品
新社会人にとっては、日々の生活に役立つ返礼品を選ぶことがポイントです。高額な家電よりも、毎日使う食品や日用品を中心に選ぶことで、節約効果を実感しやすくなります。
地域の名産品や地元の特産を選べば、ふるさとへの思いも込められます。
一人暮らしにうれしい食品・日用品
一人暮らしを始めた新卒には、保存がきく食品や生活必需品が人気です。冷凍肉や魚、レトルトご飯などは、忙しい平日の食事準備に重宝します。トイレットペーパーや洗剤などの消耗品も、買い物の手間が省けるため実用的です。
また、コーヒーやお茶など嗜好品の返礼品も、リラックスタイムを豊かにしてくれます。日常に少しの贅沢を取り入れることで、仕事へのモチベーションアップにもつながるでしょう。
仕事や生活の質を上げる便利グッズ
デスクワークが中心の新社会人には、生活を快適にする家電や雑貨もおすすめです。コードレス掃除機や加湿器、コーヒーメーカーなどは、一人暮らしの部屋を整えるのに役立ちます。 最近では、省エネ性能が高いエコ家電や、スマート家電など便利な返礼品も増えています。
長く使える品質の良い製品を選ぶことで、節約と快適さを両立できます。寄付を通して得られる“暮らしの充実”を意識して選ぶと、ふるさと納税をより楽しめます。
新卒1年目のふるさと納税に関するよくある質問
Q1. 新卒1年目でもふるさと納税はできますか?
A. はい、できます。
ただし、1年目は「住民税」の支払いがまだ始まっていないため(住民税は前年の所得に対して課税されるため)、「所得税からの控除」と「翌年(2年目)の住民税からの控除」という形になります。
つまり、今の税金が安くなるわけではなく、来年の税金の前払いをして、返礼品をもらうイメージです。
Q2. 年収がまだ分かりませんが、どうすればいいですか?
A. 毎月の給与明細から予測しましょう。
(月収×12ヶ月)+(冬のボーナス予測額)=見込み年収
という計算式で大まかな年収を出せます。ただし、ギリギリまで寄付すると限度額を超えるリスクがあるので、予測額より少し少なめに寄付するのが安全です。
Q3. ワンストップ特例申請って何ですか?
A. 確定申告をしなくても控除が受けられる制度です。
新卒の会社員であれば、寄付先の自治体に申請書(またはアプリ申請)を出すだけでOK。確定申告よりも圧倒的に簡単なので、基本的にはこちらを利用しましょう。
Q4. 実家暮らしでもメリットはありますか?
A. はい、あります。
実家暮らしでも、ご自身の年収に応じた控除限度額は変わりません。食費の足しになるお米や、家族みんなで食べられるお肉などを貰えば、親御さんにも喜ばれます。
新卒1年目のふるさと納税に関するよくある質問
Q1. 新入社員(1年目)でもふるさと納税はできますか?
A. はい、可能です。
ただし、1年目はまだ住民税を払っていないため、今年寄付した分は「来年(2年目)の住民税」から控除されます。
今の給料の手取りが増えるわけではありませんが、来年6月からの住民税が安くなるという「未来への投資」になります。
Q2. 源泉徴収票がまだないですが、限度額はどう計算しますか?
A. 「(毎月の額面給与 × 12ヶ月)+(ボーナスの見込み額)」で、おおよその年収を計算してください。
新卒の場合、計算より実際の年収が低くなる(残業が少なかった等)リスクがあるため、算出された限度額の7〜8割程度に抑えて寄付をするのが安全です。
Q3. 実家暮らしだと、一人暮らしより損をしますか?
A. いいえ、損はしません。
ふるさと納税の限度額は「年収」と「家族構成(扶養している家族がいるか)」で決まります。「実家暮らしか一人暮らしか」は計算に関係ありません。
ただし、親の扶養に入り続けている場合は限度額が変わるため、親の扶養から外れているか確認しましょう。
Q4. 確定申告は必要ですか?やり方が分かりません…
A. 会社員(給与所得者)であれば、「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告は不要です。
寄付先の自治体数が5つ以内であれば、スマホや郵送で申請書を出すだけで手続き完了です。新卒の方のほとんどはこの方法で簡単に済ませています。
まとめ | 賢い新卒は始めている!「還元」と「節税」で同期に差をつけろ
「新入社員だからまだ早い」と思っている間に、賢い同期はすでにふるさと納税を始め、将来の住民税を安くしつつ、ちゃっかりお小遣い(ポイント)まで手に入れています。ただ税金を払うだけの「搾取される側」で終わるか、制度を利用して「得をする側」に回るか。その差は、今ここで動くかどうかで決まります。
まずはシミュレーションで自分の「武器(限度額)」を把握してください。そして、その武器を最大限に活かすために、「ふるなび」のコイン還元や、「ふるさと本舗」のAmazonギフトカード還元を選んでください。
自己負担2,000円すらもポイントで回収し、実質タダで特産品を手に入れる。そんな「強かな節約術」を身につけたあなたなら、これからの社会人生活もきっと賢く生き抜いていけるはずです。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介
ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介 ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント
ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点 ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説