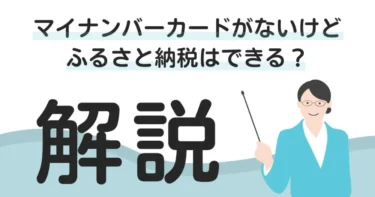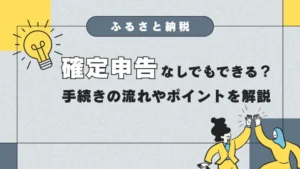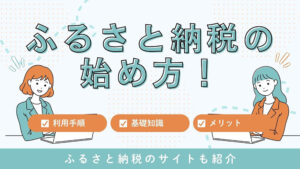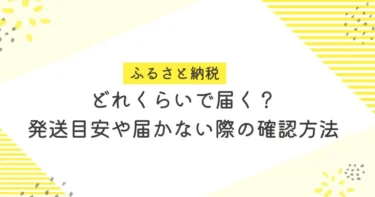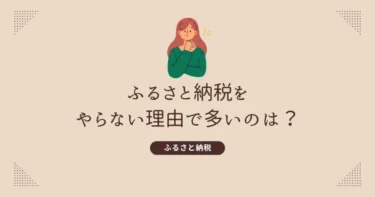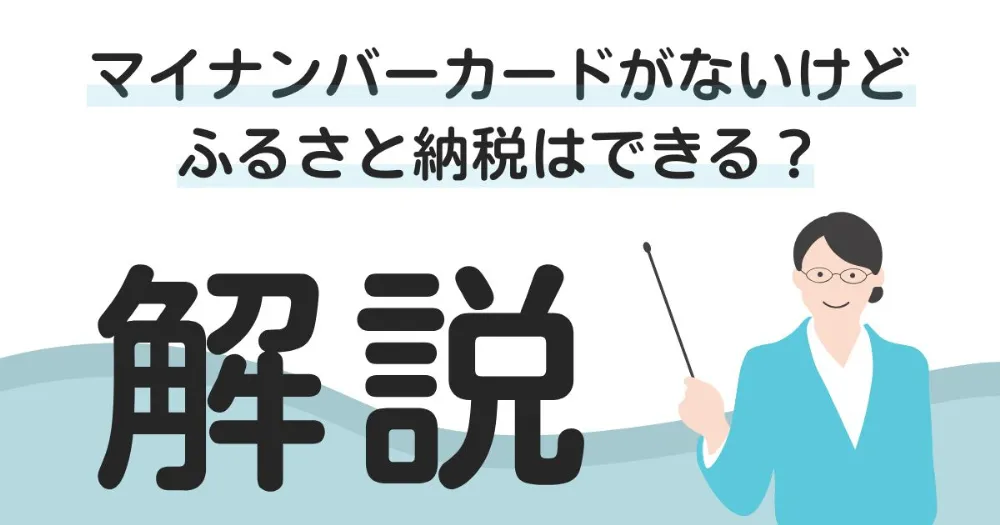
「ふるさと納税をしたいけれど、マイナンバーカードを持っていないからできないのでは?」と不安に思う方は少なくありません。結論から言うと、カードがなくてもふるさと納税は可能です。利用できる制度を理解すれば、必要な書類をそろえて問題なく控除を受けられます。
ただし、ワンストップ特例制度を使えない場合や、確定申告の手間が増えるなど、不便や損につながる場面もあるため注意が必要です。
この記事では、マイナンバーカードがない場合に選べる手続きの方法や気をつけたいポイントを整理しました。さらに、実際の申し込みの流れや人気の返礼品も紹介するので、手元にカードがなくても安心して寄附を始められるはずです。
マイナンバーカードがなくてもふるさと納税はできる?

マイナンバーカードがないと寄附できないと考える方は多いですが、実際には手続きの仕組みを理解すれば利用は可能です。
制度の選び方によって必要な準備が変わり、書類の種類や控除の受け方にも違いが出てきます。最初に全体像を知っておくことで、無理なく安心して寄附を始められるようになります。
カードなしでも可能な理由
ふるさと納税の控除は「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のどちらかで手続きします。カードがない場合でも、番号確認書類として有効なもの(例:氏名・住所が住民票と一致する「通知カード」、または「個人番号が記載された住民票の写し」)と、運転免許証などの本人確認書類を組み合わせれば申請できます。
なお、通知カードの再発行はなく、氏名や住所が変わっていると番号確認書類として使えないため、その場合は番号記載の住民票を用意します。「個人番号通知書」は番号確認書類として使えない点にも注意してください。カードがなくても必要書類がそろえば控除の手続きは問題なく完了します。
ワンストップ特例制度との違いを理解
ワンストップ特例は、年間の寄附先が「5自治体以内」で、もともと確定申告が不要な人が使える仕組みです。各自治体へ申請書と確認書類を送れば、原則として確定申告は不要になり、控除は翌年度の住民税から反映されます。
一方で、寄附先が「6自治体以上」になったり、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告が必要になったりすると、ワンストップ特例は適用できません。その場合はすべての寄附をまとめて確定申告で手続きします。自分の寄附数や申告の要否を先に確認して、どちらの方式を選ぶかを決めると迷いが減ります。
マイナンバーカードがない場合の手続き方法

カードが手元にない場合でも、寄附を進めるルートはいくつかあります。それぞれの方法には提出先や必要書類の違いがあり、準備の仕方によってかかる手間も変わります。まずは利用できる仕組みを理解し、自分の生活スタイルや寄附予定額に合った方法を選ぶことが大切です。
以下のように、カードがなくても選べる代表的な手続きの流れがあります。それぞれの特徴を知っておくことで、自分に合った申請方法を見つけやすくなります。
- 確定申告を利用して寄付する方法
- 紙申請で必要になる本人確認書類
- 申告書の提出先と提出期限
- マイナンバー通知カードや住民票での対応可否
それぞれ順番に解説していきます。
確定申告を利用して寄付する方法
確定申告では、寄附ごとに届く「寄附金受領証明書」を集めるか、ポータルが発行する「寄附金控除に関する証明書(電子)」を使ってまとめて申告します。紙で申告する場合は申告書に個人番号を記入し、番号確認書類と本人確認書類の写しを添付します。
e-Taxを使う場合は、マイナンバーカード方式のほか、税務署で発行を受けた「ID・パスワード方式」でも送信できます。カードがない人は紙申告でも十分に手続きでき、添付書類の不備を避ければスムーズに受理されます。寄附内容は控除対象分のみを正確に転記し、決済手数料など控除できない費用を混ぜないよう、受領証の記載を丁寧に確認してください。
紙申請で必要になる本人確認書類
ワンストップ特例や紙の確定申告で必要になる書類は「番号確認」と「本人確認」の2系統です。番号確認は、氏名・住所が住民票と一致する有効な通知カード、または「個人番号が記載された住民票の写し」を使います。本人確認は、運転免許証やパスポートなど顔写真付き公的身分証の写しを用意します。
顔写真がない健康保険証などを使う場合は、補助書類の追加を求められることがあります。通知カードは再発行がなく、記載事項に変更があると使えないため、その際は住民票の写しを選ぶのが安全です。封入時は各写しが鮮明に読めるかを確かめ、申請書の住所表記と完全に一致させると差し戻しを防げます。
申告書の提出先と提出期限
提出先は手続きによって異なります。ワンストップ特例は寄附先ごとの自治体へ送付し、翌年の「1月10日」必着が期限です。年末は郵便が混み合うため、早めに作成して投函すると安心です。確定申告を選ぶ場合は、所轄の税務署に提出します。e-Taxで送るか、窓口または郵送で提出するかを選べます。
確定申告の期間は例年「2月中旬〜3月中旬」が目安ですが、年度によって細部が変わるため、国税庁の案内で最新の期間を確認してください。どちらの方式でも、住所や氏名の表記揺れ、不鮮明な書類、添付漏れがあると処理が遅れます。提出物のチェックリストを作り、封入前にひとつずつ確認すると安心です。
マイナンバー通知カードや住民票での対応可否
通知カードは「紙のカード」で、顔写真がないため本人確認書類とは併用が必要です。通知カードの記載と住民票の情報が一致していれば、番号確認書類として使えます。ただし、通知カードは廃止済みで再発行はできません。氏名や住所が変わっている人、紛失している人は、番号が記載された住民票の写しを取得してください。
また、通知カード廃止後に配布される「個人番号通知書」は、番号確認書類としては使えません。書類選択を間違えると受理されないため、手元のカードの記載を確認し、必要に応じて住民票の写しに切り替えると安全です。
マイナンバーカードがないと損をする可能性があるケース
ふるさと納税は誰でも利用できる制度ですが、カードを持たないことで不便が生じたり、余分な手間が発生したりすることがあります。
寄附先の数や申告方法によっては控除が受けにくくなる場面もあるため、事前に起こり得るリスクを理解しておくと落ち着いて対処できます。
ワンストップ特例制度を使えない場合
年間の寄附先が「6自治体以上」になるとワンストップ特例は使えません。さらに、医療費控除や寄附以外の控除で確定申告が必要な年は、ワンストップの申請を出していても効力がなくなります。結果として、寄附を分けて行った場合でも、すべてを確定申告でまとめ直す必要が生じます。
年末に駆け込みで複数自治体へ寄附する予定がある人は、寄附数の見込みを早めに確認し、特例でいけるか、最初から確定申告に備えるかを決めておくと混乱を防げます。
寄付上限額を正確に把握できない場合
寄附の上限額は年収や家族構成で変わります。カードを使ったマイナポータル連携では一部の証明書情報を取り込みやすくなりますが、カードがない場合は手元の源泉徴収票や控除証明書を見ながら試算し、寄附額を調整します。情報を手入力する分、見落としや計算違いが起きやすく、控除しきれないリスクが高まります。
源泉徴収票や保険料控除証明書などを早めにそろえ、上限を余裕を持って下回る設定にすると、過不足の不安が和らぎます。迷うときは年内の寄附を小刻みに分け、上限を越えない範囲で追加する方法が役立ちます。
確定申告の手間や時間が増える場合
カードがあればe-Taxの電子署名で一気に送信できますが、カードがない場合は紙提出やID・パスワード方式の準備が必要です。紙は書類の印刷・封入・郵送に時間がかかり、ID・パスワード方式は事前に税務署で発行手続きが必要になります。
また、メッセージボックスの一部閲覧などでは電子証明書が求められる場面があるため、確認作業に手間取ることがあります。時間に追われやすい人は、早めの準備や提出手段の選定を行い、無理のないスケジュールを組むと安心です。
返礼品の受け取りが遅れるリスク
返礼品の発送は基本的に寄附の受付順や在庫状況で決まるため、カードの有無が直接の遅延要因にはなりません。ただし、ワンストップ特例の申請書類で住所が住民票と一致していない、書類が不鮮明といった不備があると、自治体からの連絡や確認に時間がかかり、結果として発送スケジュールの調整に影響することがあります。
寄附時の氏名・住所・電話番号の表記を住民票とそろえ、申請書と添付書類の記載を一致させることで、余計な往復連絡を防げます。年末の繁忙期はとくに早めの手配が安心です。
カードなしでも簡単!書類作成サポートが充実の9サイト
マイナンバーカードを持っていない場合、便利な「スマホだけで完結するワンストップ申請」は利用できませんが、「申請書を郵送」するか「確定申告」をすれば問題なくふるさと納税が可能です。
重要なのは、面倒な申請書の記入を省略できる「申請書自動作成機能」があるサイトや、郵送の手間(切手代や封筒準備)を補って余りある「高還元キャンペーン」があるサイトを選ぶことです。
アナログ派の方や、カード発行待ちの方でもストレスなく利用できる9サイトを厳選しました。
| サイト名 | カードなし時の強み | こんな人におすすめ |
|---|---|---|
| ふるなび | 還元で郵送の手間をペイ | 切手代以上に得したい人 |
| さとふる | 書類作成・管理が簡単 | 記入ミスを防ぎたい人 |
| ふるラボ | 動画で安心感 | 失敗したくない慎重派の人 |
| ニッポン | 丁寧な解説付き | アナログ手続き派の人 |
| マイナビ | 10%還元が強力 | 手間賃として還元が欲しい人 |
| ふるさと本舗 | 定期便で書類削減 | 申請書の枚数を減らしたい人 |
| au PAY | 情報入力の手間なし | auユーザーで楽したい人 |
| ポケマル | 生産者の温かみ | 手続きより「人」重視の人 |
| パレット | 体験型で満足感 | 書類作業を忘れて楽しみたい人 |
ここからは、それぞれのサイトが「マイナンバーカードがない方」にどう優しいのかを解説します。
ふるなび
マイナンバーカードがないと、申請書を郵送する手間がかかります。その「手間賃」と考えたいのが、「ふるなび」のコイン還元です。
寄付額に応じてAmazonギフトカードなどに交換できるコインがもらえるため、封筒や切手の準備にかかったコストや労力を十分に回収できます。マイページから申請書のダウンロードも可能なので、記入の手間も最小限です。
さとふる
「さとふる」は、マイナンバーカードを使ったアプリ申請だけでなく、郵送用の申請書作成機能も非常に使いやすいのが特徴です。マイページから住所などの情報が入力済みのPDFを簡単にダウンロードできます。
「どこに何を書けばいいかわからない」という初心者の方でも、迷わず書類を完成させることができるため、書類不備で返送されるリスクを減らせます。
【ふるラボ】放送局運営の安心感
手間をかけて書類申請するからには、絶対に返礼品選びで失敗したくないもの。「ふるラボ」なら、返礼品を動画で事前に確認できるため、写真詐欺に遭うリスクを回避できます。
「苦労して申請したのに、届いたものがイマイチ…」という悲劇を防ぎ、確実な満足を手に入れたい慎重派の方におすすめです。
ふるさと納税ニッポン!
「ふるさと納税ニッポン!」は雑誌メディア発のサイトということもあり、手続きの解説が非常に丁寧です。デジタル申請に頼らず、紙での申請を基本とした分かりやすいガイドがあるため、マイナンバーカードがない方でも迷わず手続きを進められます。
昔ながらの丁寧な対応を好む方に、ぴったりのサイトです。
マイナビふるさと納税
書類のコピーを取ったりポストに投函したりするのが面倒だと感じるなら、「マイナビふるさと納税」の10%還元をモチベーションにしましょう。
数万円の寄付で数千円分のAmazonギフトカードが戻ってくると思えば、コピー代や少しの手間など安いものです。「面倒くさい」を「お得」で上書きできる、合理的な選択肢です。
ふるさと本舗
ワンストップ特例申請は「寄付ごとの提出」が必要なため、回数が多いと書類作成も大変です。そこで「ふるさと本舗」の定期便を活用しましょう。
1回の申し込みで数ヶ月分の返礼品が届くタイプなら、申請書の提出は1枚で済みます。マイナンバーカードがなくて書類作成が面倒な方こそ、定期便で「申請回数」を減らすのが賢いテクニックです。
au PAY ふるさと納税
マイナンバーカードがなくて身分証のコピーなどが必要な分、申し込み時の入力作業くらいは楽をしたいもの。「au PAY ふるさと納税」なら、au IDと連携するだけで住所などの入力が不要になります。
Pontaポイントも使えるため、手続きの手間とお金の負担の両方を減らして、気軽にふるさと納税を始められます。
ポケマルふるさと納税
デジタルな手続きが苦手な方でも、「ポケマルふるさと納税」なら生産者との温かいやり取りが楽しめます。通知カードのコピーを用意するといった事務作業も、美味しい食材を届けてくれる生産者への「お礼の手紙」を書くような感覚で行えるかもしれません。
効率化だけでなく、アナログな「人のぬくもり」を感じたい方におすすめです。
ふるさとパレット
「書類手続きが面倒だな…」というネガティブな気持ちを、「旅行が楽しみ!」というポジティブな気持ちに変えてくれるのが「ふるさとパレット」です。
東急グループのホテルやレストランを利用できるチケットなら、利用時に「あの時、書類を頑張って書いてよかった」と思える素敵な体験が待っています。事務作業の先にある楽しみを重視する方におすすめです。
ふるさと納税の申し込み手順を具体的に解説
寄附の流れをあらかじめ知っておけば、途中で迷うことが少なくなります。申し込みから控除までにはいくつかの段階があり、事前に確認しておくことで作業を効率的に進められます。
全体の手順を把握することが、安心して寄附を続けるための第一歩になります。
- 寄付先自治体や返礼品を選ぶポイント
- インターネットからの申し込み手順
- 寄付金受領証明書の受け取りと保管
- 控除手続きをスムーズに進めるコツ
それぞれの順番に解説していきます。
寄付先自治体や返礼品を選ぶポイント
寄附額の上限を踏まえたうえで、用途や時期に合う返礼品を選ぶと満足度が高まります。食品は消費期限と内容量、定期便は配送間隔を必ず確認します。旅行や体験型は有効期限や除外日、予約方法の条件を事前にチェックしてください。
自治体の説明欄に発送時期の目安が記載されていることが多いので、必要なタイミングに届くかも見ておくと安心です。寄附先の使い道指定ができる場合は、防災や子育て支援など、自分が応援したい分野を選ぶと納得感が増します。
インターネットからの申し込み手順
寄附サイトで会員登録を行い、希望の返礼品を選択します。寄附者情報の入力時は、氏名・住所・生年月日を住民票と同じ表記にそろえます。ワンストップ特例を使うかどうかを選択し、使う場合は自治体ごとの申請書送付方法を確認してください。
支払い方法を選び、申込内容を最終確認して確定します。完了メールやマイページの申込履歴は、受領証や申請書の到着時期を把握する目安になります。入力のやり直しが発生しないよう、住所の番地や建物名、電話番号まで丁寧に見直しましょう。
寄付金受領証明書の受け取りと保管
寄附後は自治体から「寄附金受領証明書」が届きます。確定申告では寄附ごとの証明書をまとめて提出するか、対応ポータルで発行される「寄附金控除に関する証明書(電子)」で一括提出が可能です。電子の証明書は、マイナポータル連携などで取得しやすく、添付の手間が減る点が便利です。
紙の証明書を使う場合は、封筒やファイルに年別で保管し、申告時にすぐ取り出せるように整理してください。ワンストップ特例を使う年は提出対象ではありませんが、寄附内容の確認のために保管しておくと安心です。
控除手続きをスムーズに進めるコツ
まず、年内の寄附計画と寄附先の数を早めに決めます。ワンストップ特例を使うなら、申請書の記入と必要書類のコピーを寄附の都度進め、年末の作業を分散させます。確定申告を選ぶ場合は、受領証の保管と寄附履歴の突合を年内から始め、申告期間の開始直後に提出できる状態に整えます。
住所・氏名の表記は住民票と完全一致させ、添付書類は鮮明な写しを用意します。迷った箇所は早めに自治体や国税庁の案内で確認し、期限に余裕を持って提出すれば、控除漏れの不安が小さくなります。
マイナンバーカードがなくても選べるおすすめ返礼品

寄附で選べる返礼品は非常に幅広く、暮らしを支える実用品から特別な体験まで多彩です。カードの有無に関係なく楽しめる品ばかりなので、寄附先を考える際には生活や趣味に合わせた選び方ができます。
どんな分野に人気が集まっているのかを知ると、選ぶときの参考になります。
旅行や宿泊体験が楽しめる返礼品
旅行券や宿泊券といった体験型の返礼品は、家族の記念日や友人との特別な時間に活用できる点が魅力です。有効期限の長さや除外日を事前に確認しておけば、計画に合わせて無駄なく利用できます。食事券と組み合わせて使えるプランもあり、現地での滞在をより充実させてくれます。
マイナンバーカードを持っていなくても問題なく申し込み可能で、控除の仕組みを理解しておけば安心して選べます。
地域の特産品や食品カテゴリー
米や肉、魚介、果物といった地域ならではの特産品は根強い人気を誇ります。定期便を選べば毎月届く楽しみがあり、家庭の食卓を豊かに彩ってくれます。冷凍保存できる商品や長期保存可能な加工品も多いため、家族構成や生活スタイルに合わせて無理なく消費できます。
マイナンバーカードがなくても寄附後に受領証が届くので、安心して日常使いできる食品を選べるのが魅力です。
日用品や実用的な返礼品
トイレットペーパーや洗剤などの日用品は、毎日の生活に欠かせないものをストックできる便利さがあります。量が多いセットは単価がお得になる一方、保管場所を確保しておく必要があるので注意が必要です。
さらに、省エネ家電や調理器具など長く使えるアイテムも返礼品として人気を集めています。マイナンバーカードの有無にかかわらず選べるため、暮らしを少し豊かにしたい人や実用性を重視する人に向いています。
まとめ | カードがなくてもメリットは変わらない!
マイナンバーカードがないと「オンライン申請」という時短技が使えないだけで、税金の控除額や返礼品のお得さは全く変わりません。
通知カードや免許証のコピーを用意するのは少し手間ですが、「さとふる」などで入力済みの申請書を印刷したり、「ふるさと本舗」の定期便で申請回数を減らしたりと、工夫次第で楽はできます。
「カードがないから」と諦めずに、ぜひポイント還元や美味しい返礼品を受け取ってくださいね。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介
ふるさと納税2026年1月2日ふるさと納税でおすすめの家電・電化製品!還元率の高いお得な商品を紹介 ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント
ふるさと納税2026年1月1日ふるさと納税の控除の確認!住民税決定通知書の見方や確認すべきポイント ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税して会社に副業がバレる?確定申告時のポイント・注意点 ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説
ふるさと納税2025年12月30日ふるさと納税はリピートできる?条件やメリット・注意点を解説